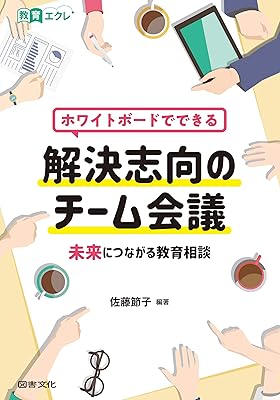「学校全体の生徒指導の対応力を、実践的に高めたい…」
そんな願いを持っている先生方におすすめなのが、「インシデント・プロセス法」です。
1時間ほどの校内研修で、事例を題材に検討を行い、教職員全体の対応力を育成できます。
このコラムを読むと、実践したくなる「安全・安心な事例研究会」を学ぶことできます。
内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。
このコラムは約3分で読めます。
1 インシデント・プロセス法とは
簡単に言うと、
ある出来事(インシデント)を話の起点に
参加者が背景情報を集め、支援策を考える
という手順(プロセス)の話し合い
ある出来事(インシデント)を話の起点に、参加者が背景情報を集め、支援策を考える
という手順(プロセス)の話し合い
マサチューセッツ工科大学(MIT)のピコーズ教授夫妻により、考案された事例研究法です。
「事例研究法」は、いわゆるケース会議とは、少し異なります。
<共通点>
・参加者全員で事例を考察し、新たな支援策を導き出すこと
<相違点>
・参加者全員の成長を目的の一つとしている
・当該児童生徒を知らない教職員も含めて話し合う
・早急な対応を要する事例は対象にしない
このような特徴から、校内研修に非常に適していると考えられます。
(1)全体の流れ
4つのステップで構成されています。

事例提供者が出来事を説明する
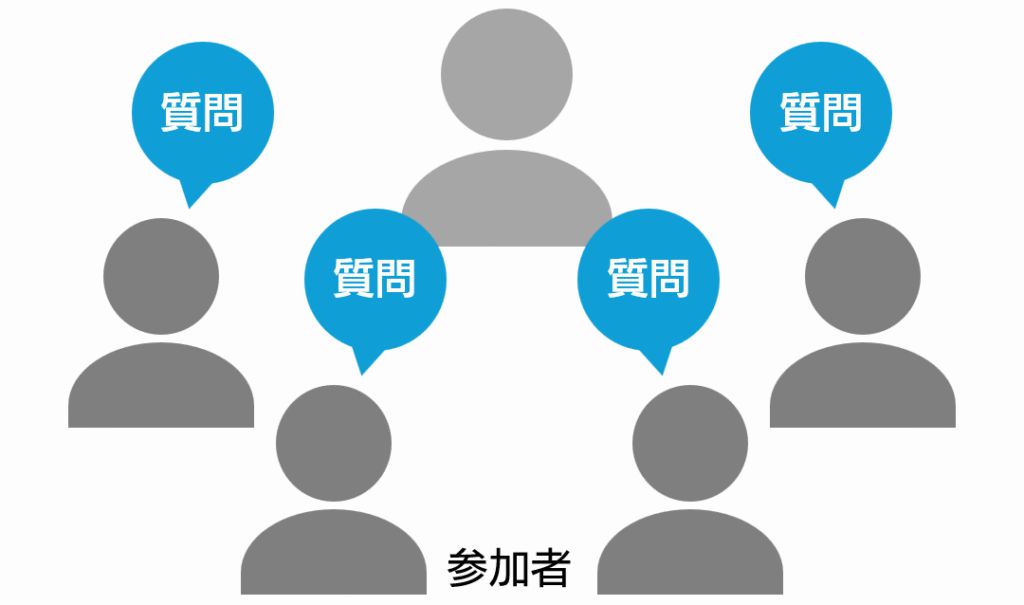
参加者が質問し、事例への理解を深める
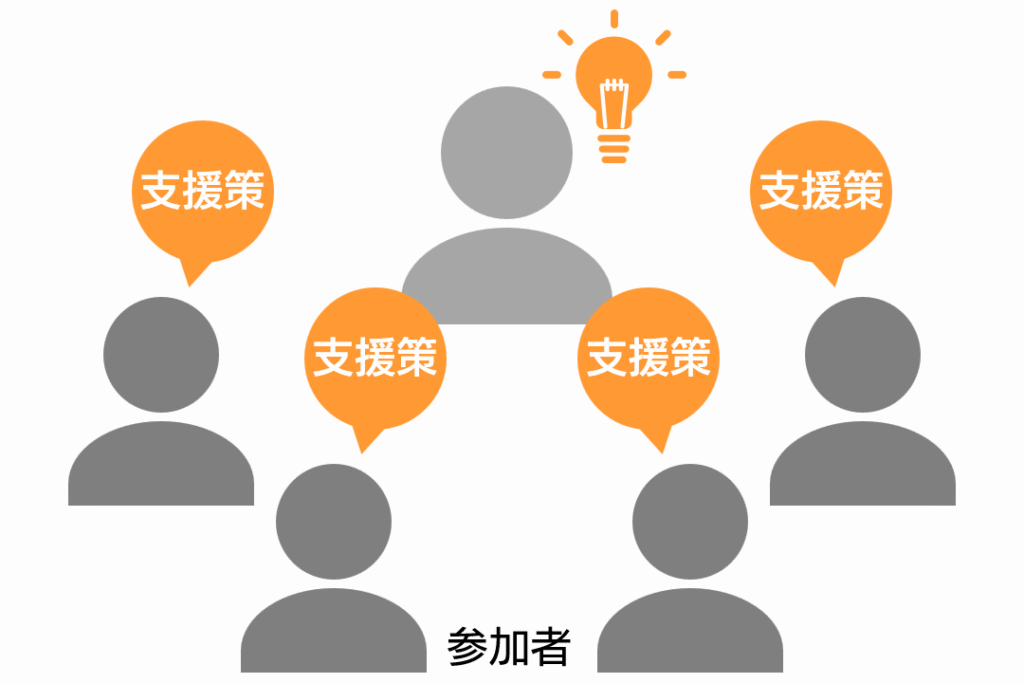
参加者が支援策を考え、提案する
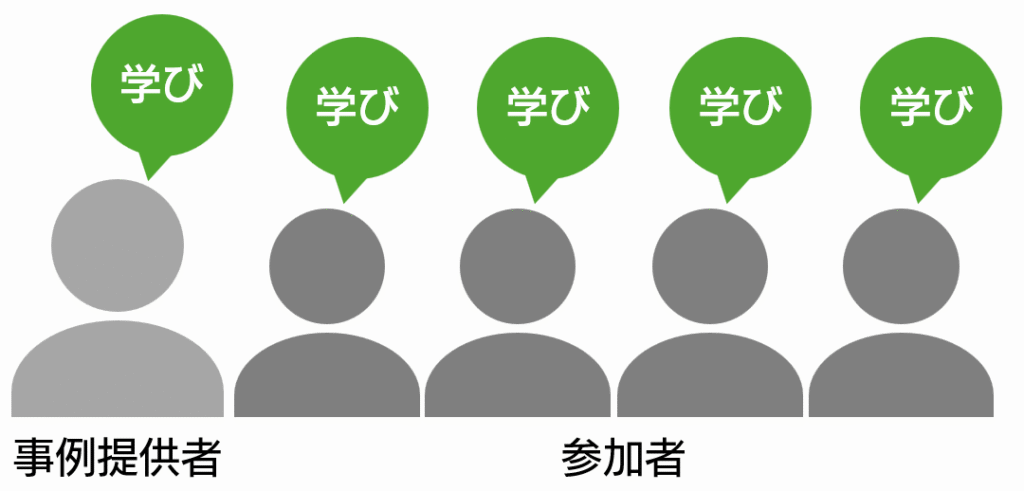
各自が学んだことを整理する
(2)ルール
安全・安心な場をつくるためのルールです。
- 資料を準備せず、個人でメモを取らない
(記録係がホワイトボードに書く) - 批判・否定はしない
- 発言はコンパクトにする
(一部の人に偏らず、発言機会を公平にする) - 積極的に発言する、ただし「パス」もOK
(3)準備
手ぶらで始められるのが、大きな特徴です。
- ホワイトボード
- タブレット(写真撮影用)
(4)参加者の役割
役割は次の4つです。
事例提供者(1人)
事例を提示し、質問に答える
ファシリテーター(1人)
進行、時間管理、雰囲気づくり
記録係(1~2人)
ホワイトボードに記入する
参加者(3~6人程度)
事例を理解し、支援策を提案する
(5)特徴
- 物理的な負担が少ない
- 事例提供者が資料を作らなくてよい
- 準備する道具がほとんど不要
- 記録はホワイトボード1枚で完結
- 心理的な負担が少ない
- 批判・否定されない
- 発言をパスできる
- 発言の機会が公平にある

2 実施方法
グループ編成:
全教職員で実施する場合は、8~10人程度のグループを複数作ります。
会場レイアウト:
シアター型で配置します。
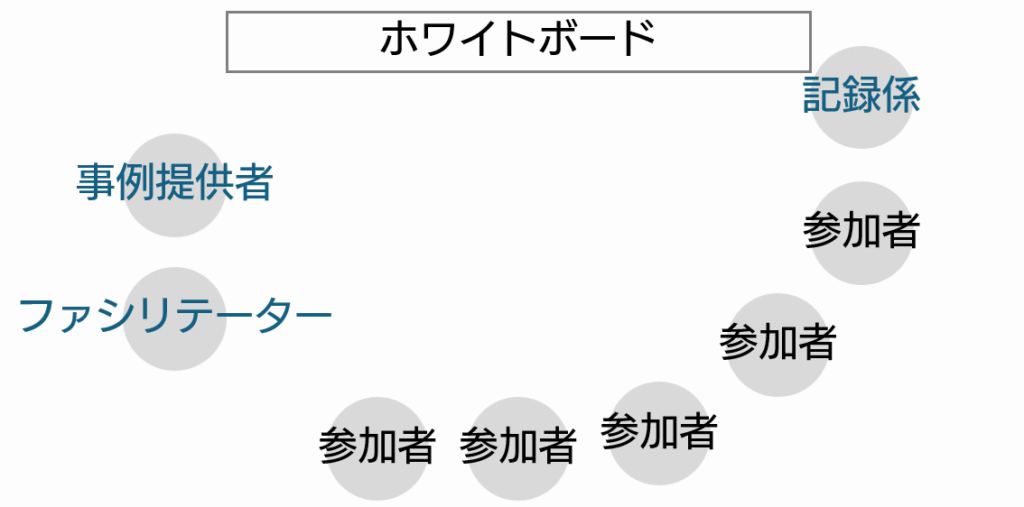
ホワイトボードの使い方:
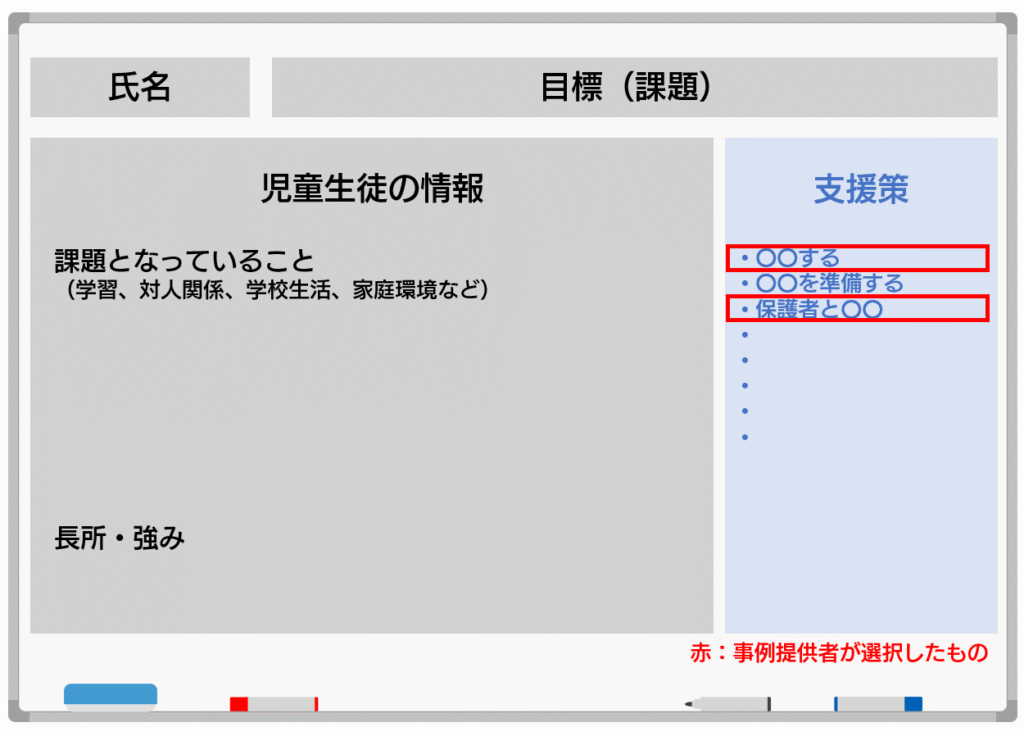
支援策は青色ペン。最後に事例提供者が「やってみたい」と選んだものが赤色ペン。
(1)事例の提示 5分
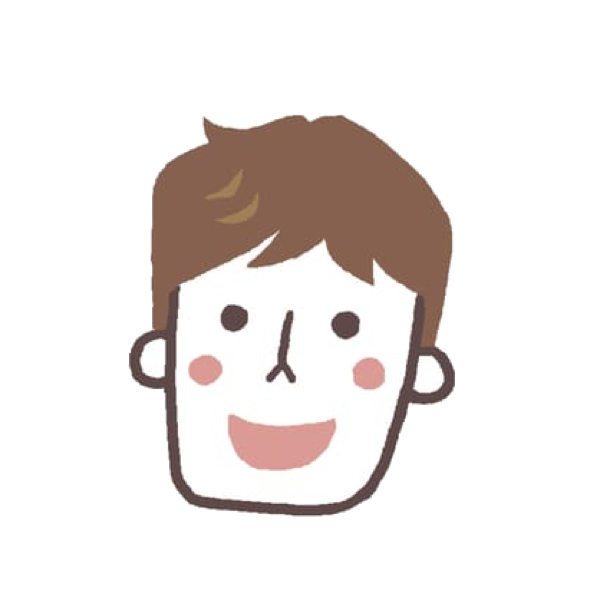 ファシリテーター
ファシリテーターこれから事例研究会をはじめます
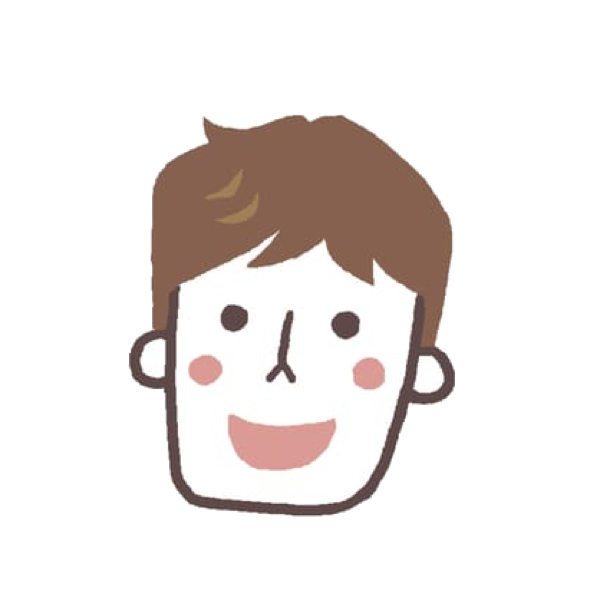 ファシリテーター
ファシリテーター時間は、「事例の提示5分」「情報収集15分」「支援策の提案15分」「まとめ10分」の合計45分です
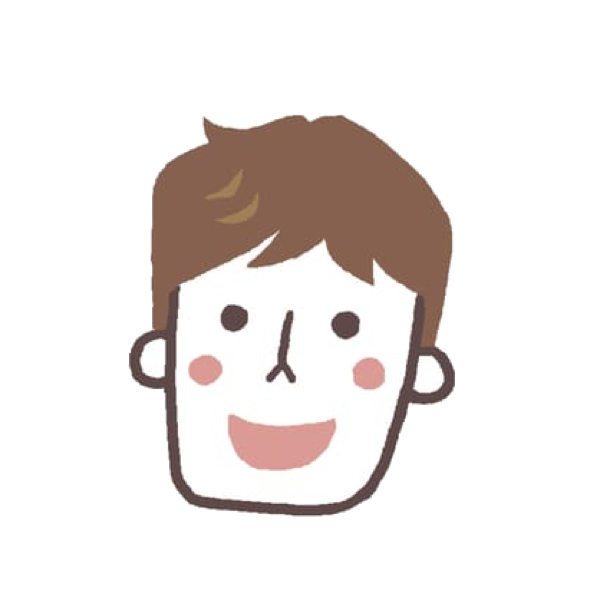 ファシリテーター
ファシリテータールールは、3つです
「①批判・否定をしない」「②発言はコンパクトに」「③積極的に発言する、ただしパスOK」です
 ファシリテーター
ファシリテーターそれでは〇〇先生から事例を提示していただきます
記録係の△△先生、記録をお願いします

事例の提示(5分)
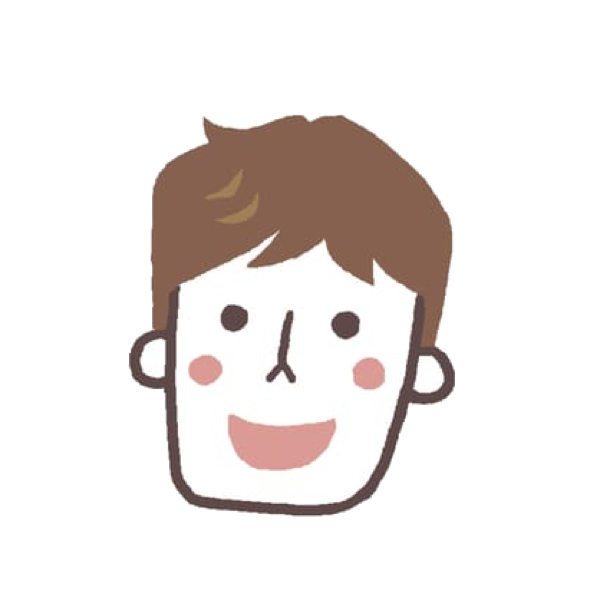 ファシリテーター
ファシリテーターありがとうございました
では、目標を設定したいと思います
気になる点は多いと思いますが、この時間でみんなで話し合うなら、どんな目標が良いでしょうか?
事例提供者の〇〇先生、お願いいたします

事例提供者が目標を設定
ポイント
- 提示時間5分は短いため、次の「情報収集」で参加者から多くの質問が出ます。
- とても忙しいのは「記録係」です。
事例提供者にゆっくり話してもらえると助かります。
(2)情報収集 15分
 ファシリテーター
ファシリテーター次は、情報収集です
支援策を考えるのに必要な情報を集めましょう
質問は簡潔に、一問一答形式でお願いします
事例提供者は事実のみを簡潔に答えてください
こちらから順番に質問して、何周か回しますので、考える時間が必要なときは「パス」でも結構です
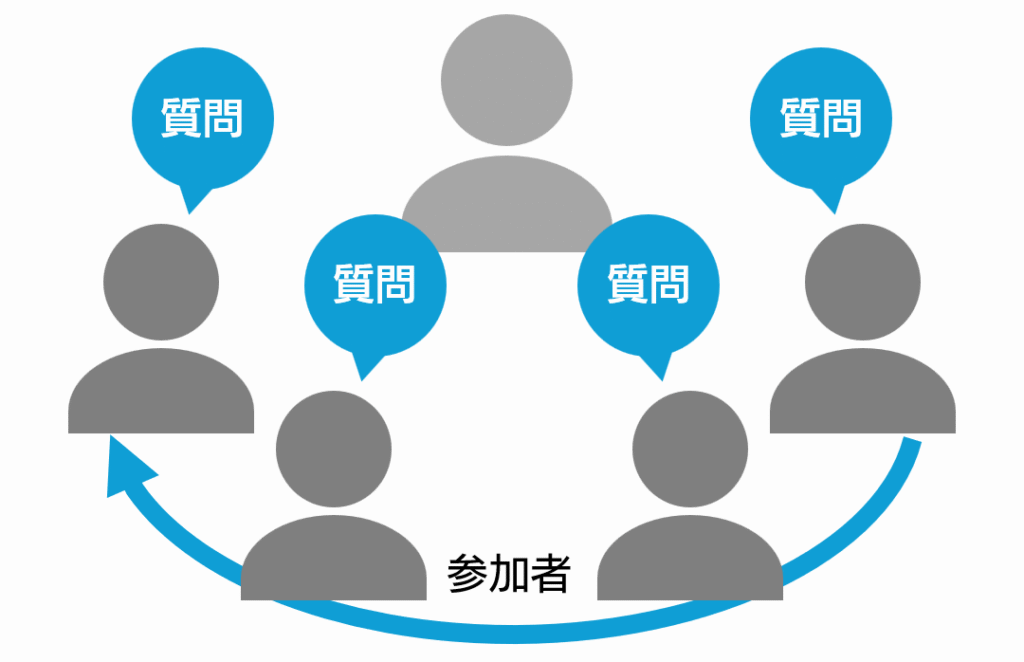
情報収集(15分)
質問例:「いつから?」「どのぐらい?」「本人は何と言ってる?」
「友だちはいますか?」「学習面はどうですか?」「得意なことは?」
 ファシリテーター
ファシリテーター(必要に応じて)
〇〇について、聞きたいことはありませんか?
 ファシリテーター
ファシリテーター(必要に応じて)
その「どうして」を探るために、みんなで考えていきましょう
そのためにほしい情報はありませんか?
ポイント
- 事例提供者が情報を持っていない場合は、「わかりません」でOK。
- 順番を回すときは、「うちわ」などをバトン代わりにするとスムーズ。
(3)支援策の提案 15分
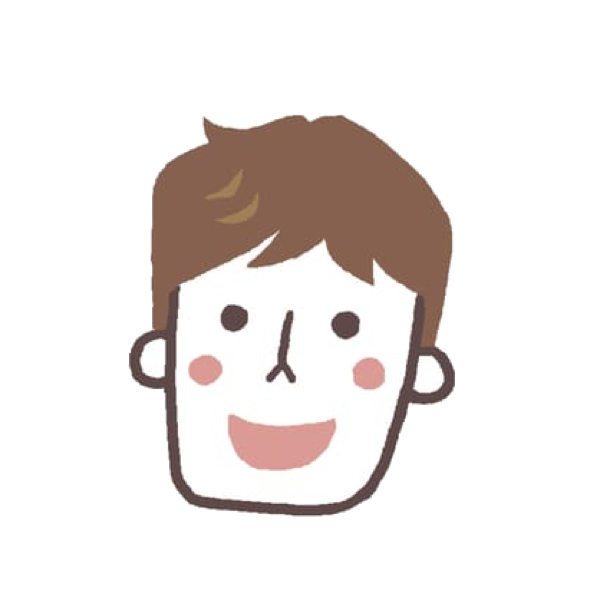 ファシリテーター
ファシリテーター次は、支援策の提案です
目標に近づくために、「明日からできそうなこと」「試してみたいこと」は何でしょうか?
お一人で考えたあと、隣の人と話し合いの時間を取ります
そして、全体に発表していただきたいと思います
まず2分間、お一人で考えてください

個人で考える(2分)
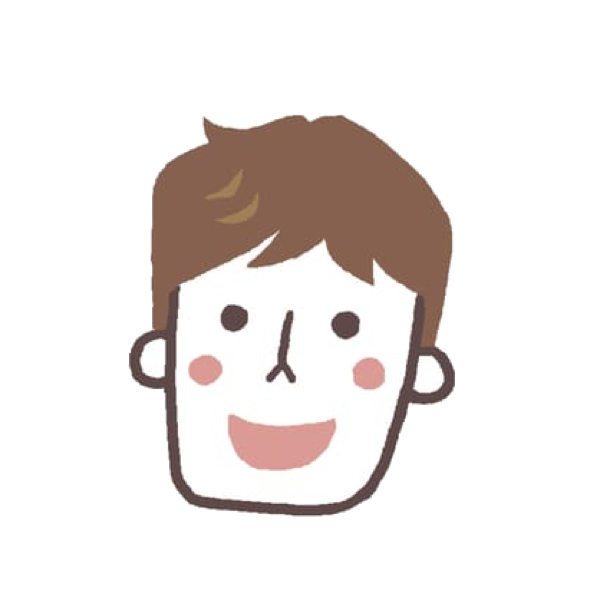 ファシリテーター
ファシリテーターでは、3分間、隣の人とペアで話し合ってください

ペアで話し合う(3分)
 ファシリテーター
ファシリテーターそれでは全体で共有します
こちらから順番に、1人1つずつ提案してください
これも何周か回したいと思います
パスも結構です
自由な発想で、質より量を意識して、お願いします
他のアイディアに便乗するのも歓迎です
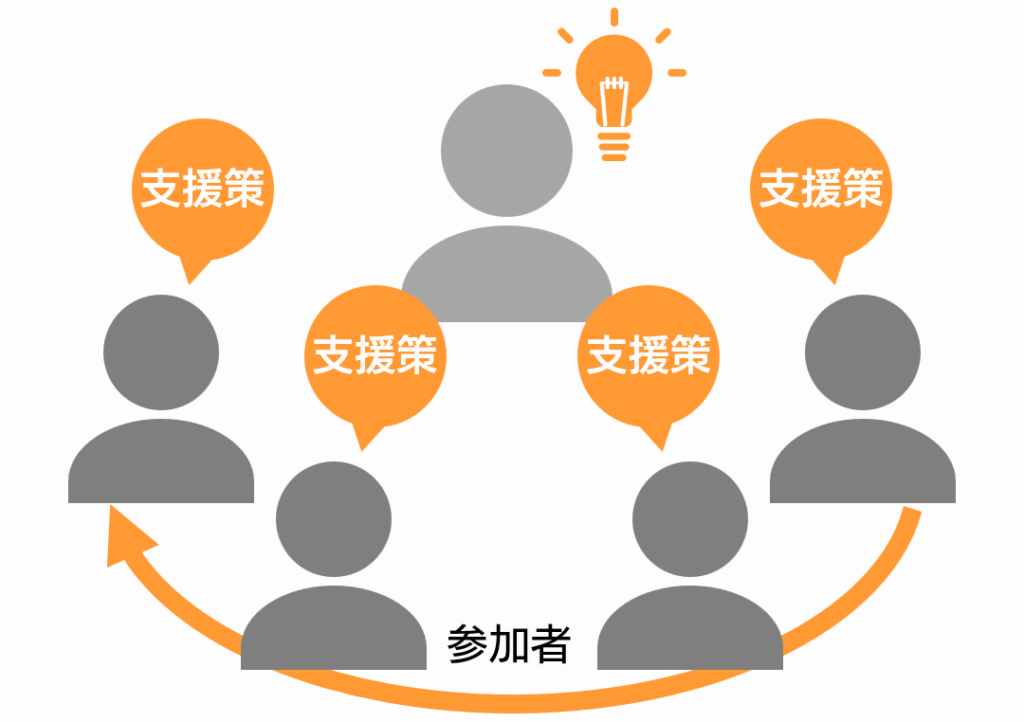
支援策の提案(約8分)
ポイント
- この時間は、参加者に「メモ用紙」を配付すると便利です。
- 支援策は「~する」「~してみる」という表現が前向きです。
- 「ペアでの話し合い」を挟む理由は、全体発表への不安を軽減するためです。
参加者が慣れている場合は、省略してよいと思います。 - 提案への良し悪しの評価はせず、テンポよく進めます。
(4)まとめ 10分
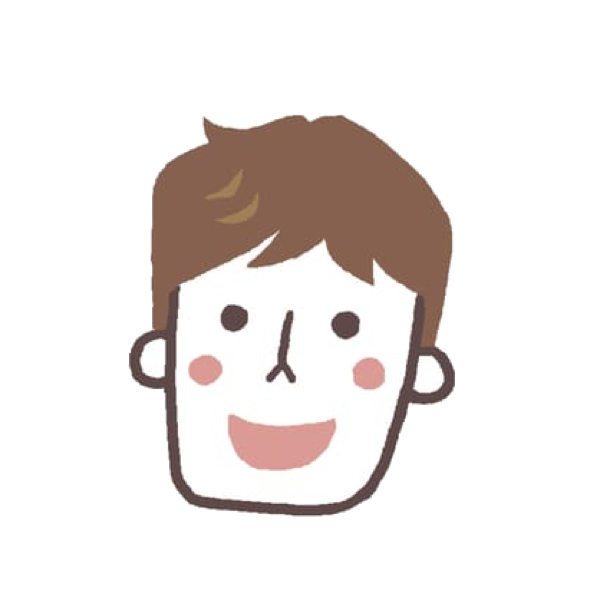 ファシリテーター
ファシリテーターありがとうござました
では、まとめに入ります
 ファシリテーター
ファシリテーターまず事例提供者の〇〇先生から、「やってみたい」と思った支援策や、全体を通して「気づいたこと」を話していただきます
続いて、参加者の皆さんから「学んだこと」「気づいたこと」を1人1分ほどでお願いします
それでは〇〇先生、3分ほどでお願いいたします
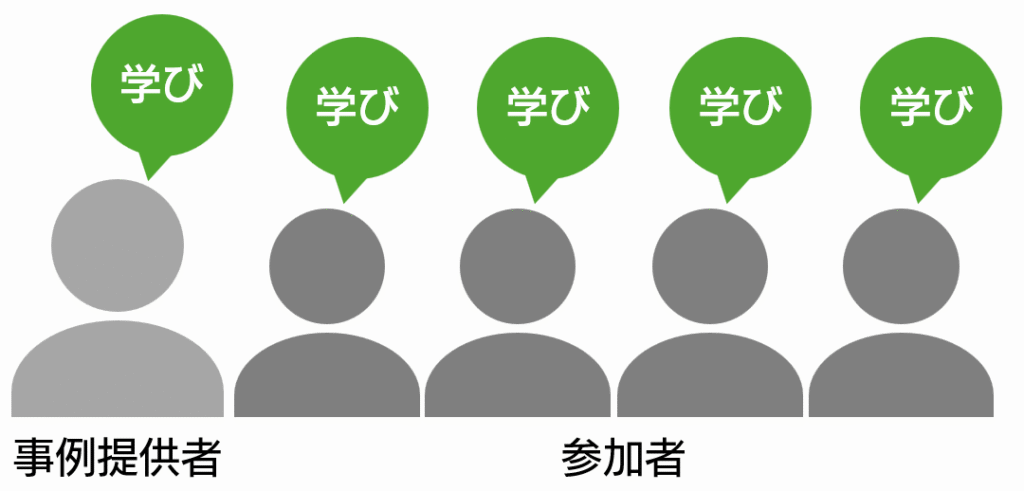
学びや気づきの共有(約8分)
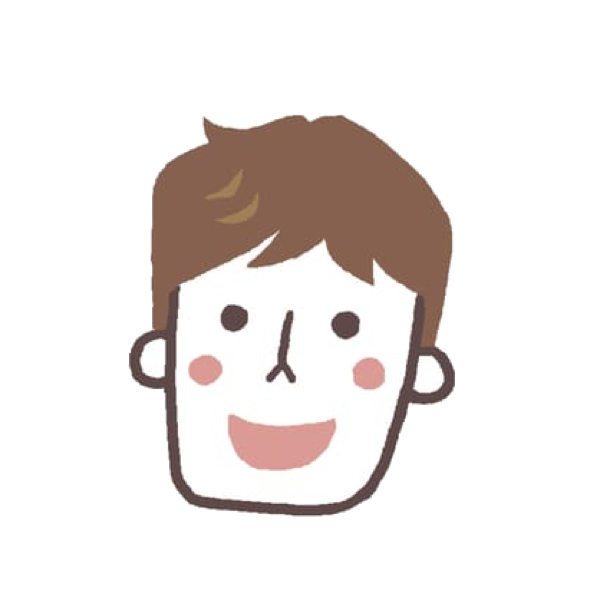 ファシリテーター
ファシリテーター事例提供してくださった〇〇先生に拍手をお願いいたします
(パチパチ)
これで事例研究会を終わります
ありがとうございました!
ポイント
- 事例提供者からは、「事例を出してよかった」「ヒントがもらえた」「うれしかった」といった感想が多いです。
- 全教職員で実施する場合は、各グループが3分ずつ発表すると、学びを共有できます。

3 チーム学校への一歩
「インシデント・プロセス法」には、次のエッセンスがあります。
- 学級担任の負担を増やさない
- 一つの事例をみんなで話し合う
- ルールやマナーを守り、安全・安心な場で話し合う
- 時間を意識して発言する
- ホワイトボードを活用して共通理解する
これらは、普段のケース会議でも大切にしたい姿です。
校内研修でこのような事例研究会を体験することで、
日常の業務にも、自然と良い雰囲気が広がっていくことを期待します。
インシデント・プロセス法は、「チーム学校」への確かな一歩となると思います。

4 スライド資料ダウンロード
本コラムの内容を、スライドと進行シートにまとめました。
ダウンロードのうえ、ご自由にご活用ください。
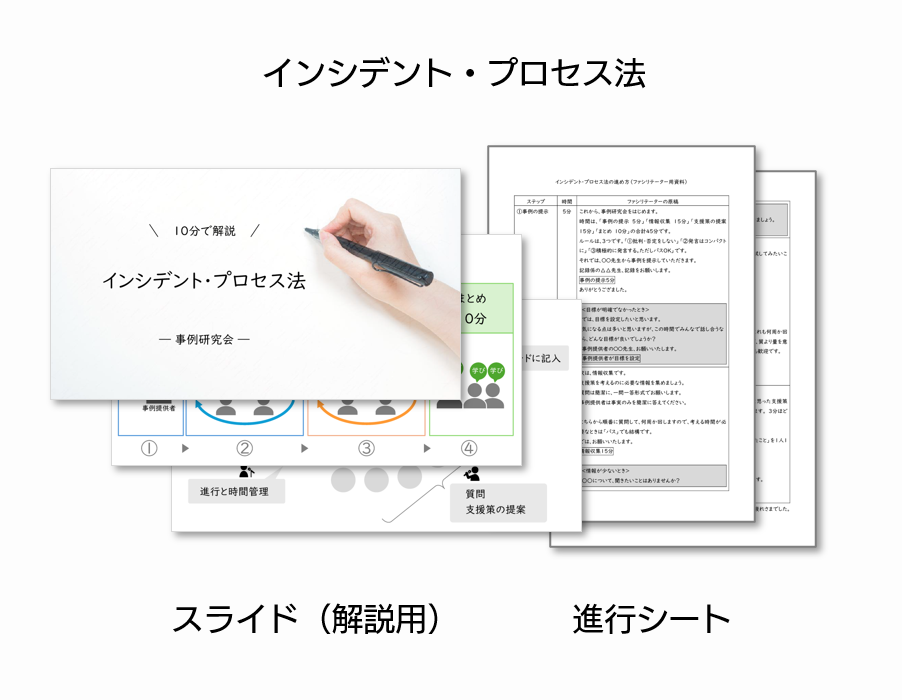
スライド(解説用)
進行シート(ファシリテーター用)
まとめ
- インシデント・プロセス法は、話し合いの手順が構造化された事例研究法です。
- ルールがあることで、安全・安心な話し合いの場をつくることができ、参加者全員の成長を目的の一つとしています。
- 良質な話し合い実際に体験できることから、教職員向けの校内研修に非常に適した手法といえます。
もっと知りたい先生へのオススメの書籍
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。
PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。
次回もどうぞお楽しみに。