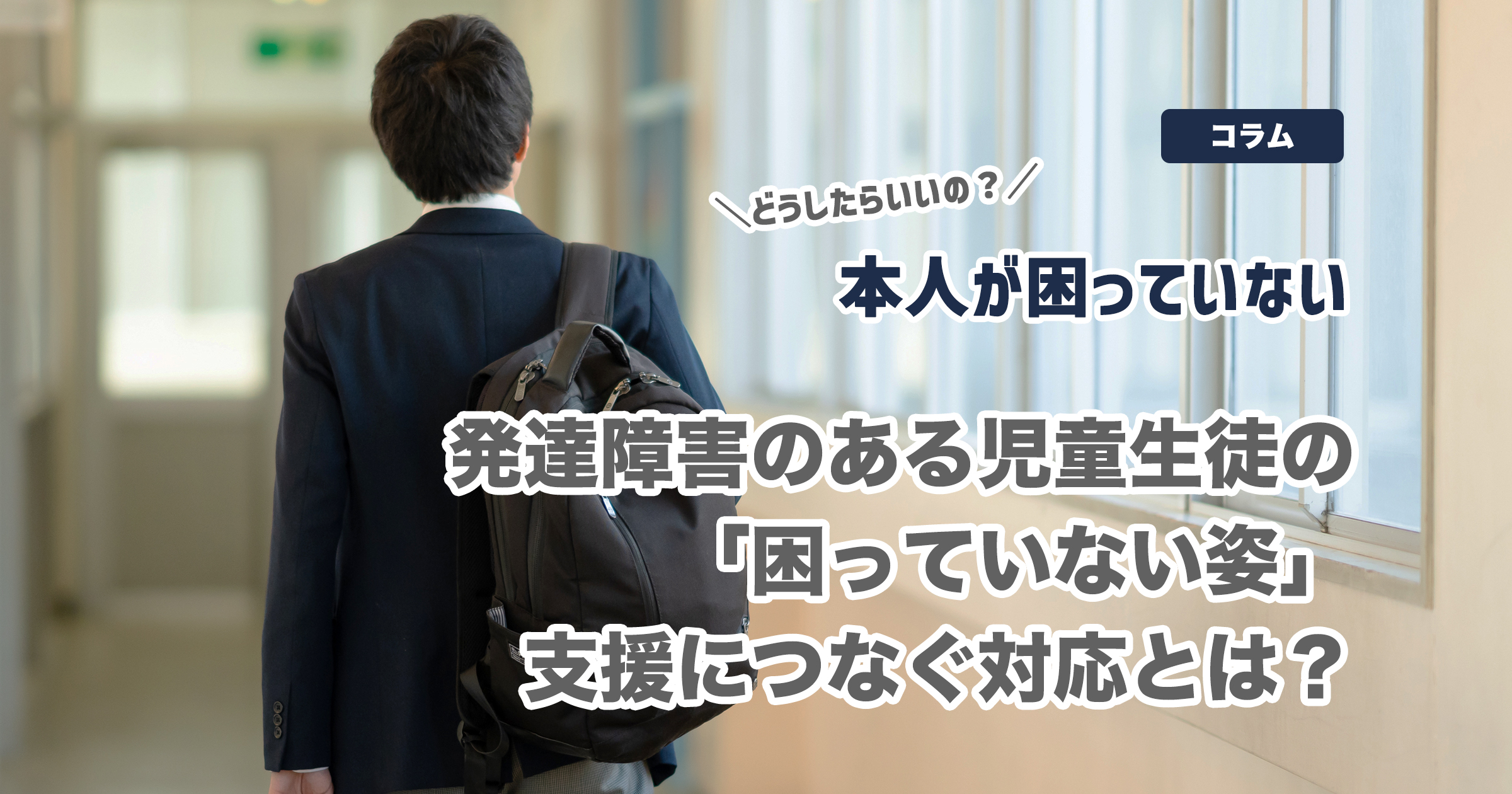発達障害(神経発達症)のある児童生徒について、
「本人が困っていないから、問題がなかなか改善されない」という悩みが、先生方から多く聞かれます。
このコラムでは、発達障害のある児童生徒の「困っていない姿」を理解するための視点と、
支援につなげるための効果的なかかわり方について、具体例を交えながら解説します。
文部科学省の表記に従い、本コラムでは「発達障害」と記載します。
内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。
このコラムは約3分で読めます。
1 「本人が困っていない」ことに悩むとき
例えば家庭では、
- 「勉強しないと後悔するよ」と声をかけても、「別にいい」と返される
- 毎朝起こすことに疲れて「そろそろ自分で起きて」と伝えても、行動が変わらない
- ゲームのやりすぎで昼夜逆転し、「相談してみない?」と声をかけても、「うるせー!」と返ってくる
何度伝えても行動が変わらず、こちらの思いが届いていないように感じると、
「痛い思いをしないと、分からないのかもしれない」
「本人が困っていないから、変わらないんだ」
と考え、どうしたらよいのか途方に暮れてしまうことがあります。
学校でも、同じような状況が見られます。
- 何度注意しても遅刻を繰り返し、これ以上言っても響かないと感じる
- イライラが目立ち、「カウンセラーに相談してみない?」と促しても拒否される
- 宿題の未提出を注意すると、言い訳を繰り返し、責任を先生に押しつけようとする
このように、指導しても行動が変わらなかったり、平然とした態度が見られたりすると、
「反省していない」
「変わる気がない」
「本人が困っていないから進まない」
と感じ、対応に悩むことも少なくありません。
特に、「周囲の児童生徒が困っている」「本人の進級や卒業が心配」といった状況では、
行動変容を急ぎたい気持ちや、先生の焦り・もどかしさも大きくなるのではないでしょうか。

2 「困っていないように見える」だけかも
次のような様子は、一見すると「困っていない」と受け取られがちです。
- 困っている表情ではなく、平気そうに見える
- 「困っている」「悩んでいる」と口にしない
- 言い訳をしたり、話題をそらしたり、開き直ったりする
しかし、発達障害のある児童生徒の場合、
「困っているけれど、そう見えないだけ」というケースが少なくありません。
自閉スペクトラム症のある児童生徒の多くは、「気持ち」より「理屈」を得意とする傾向があり、
感情を言葉や表情で表すことが苦手なため、周囲に誤解されやすい側面があります。
言い訳や開き直りのように見える言動は、
否定されてきた経験の積み重ねから生まれた、自己防衛(強い否認)であることもあります。
例えば、「〇〇が悪い」と周囲に責任を向ける発言の背景には、
これまで「あなたが悪い」と言われ続けてきた経験があり、
相手より先に「自分は悪くない」と主張することで、自分を守ろうとする心理が隠れていることがよくあります。
他人のせいにする子は
自分のせいにされてきた子

3 「困っていても、どうにもできない」のかも
「困っているなら、自分でなんとかするはず」
「行動が変わらないのは、本人が困っていないからだ」
こうした見方は一般的ですが、必ずしも正しいとは限りません。
特に、発達障害のある児童生徒は、
「困っていても、自分ではどうにもできない」状態になりやすいと考えられます。
ここで、氷山モデルをイメージしてみましょう。
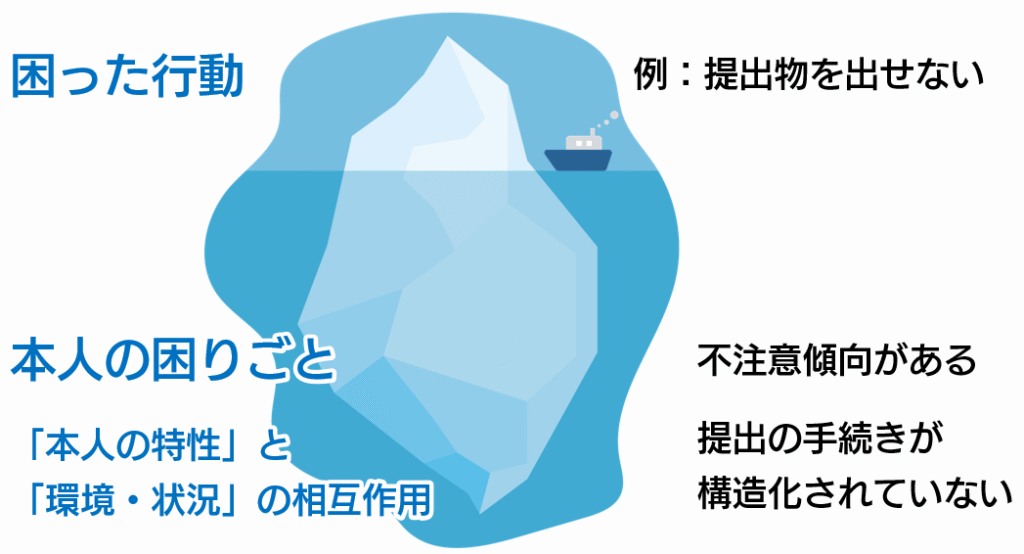
ここでの構造化は、提出物リストや、ファイルやボックスの習慣化など
ここでの構造化は、提出物リストや、ファイルやボックスの習慣化など
本人が「提出物を出せないこと」に困っていても、
その水面下には、さらに大きな「本人の困りごと」が隠れていることがあります。
そのため、「前日に準備して鞄に入れればいいのに」と言われても、
本人だけでは、それを実行するのはとても難しいことがあります。
これは、やる気や努力不足の問題ではなく、
「環境・状況を調整する」支援が必要であることを示すサインと捉えることができます。
指導しても行動が変わらない・・・
そんなときは、支援の出番です

ここまでのまとめ
- 特に発達障害のある児童生徒の場合、「困っていないように見えても、実際は困っている」「困っているけど、自分ではどうにもできず、あきらめている」ことがあります
- このような状況への対応は簡単ではありませんが、児童生徒の「見える姿」の背景で何が起きているのかに目を向け、どう話を聴き、どう支援につなぐかを考えることが大切です
4 対話を重ねるためのフレーズ
例えば、「宿題を提出しないこと」について指導したとき、
児童生徒から次のような反応が返ってくることがあります。
- 「あんなの意味がねぇし!」
- 「どうでもいい!マジで無理」
- 「だって、先生が悪いでしょ!」
このような言葉を耳にすると、先生としても反応せずにはいられません。
「そんなことを言っちゃダメでしょ」
「意味があるから出してるんだよ」
「人のせいにしない!」
こう返したくなる気持ちは当然ですが、
実際にこう返してしまうと、その後の対話が続きにくくなってしまいます。
では、どのような言葉を返したらよいのでしょうか?
おすすめのフレーズは、
 先生
先生そんなに困っていたんだね
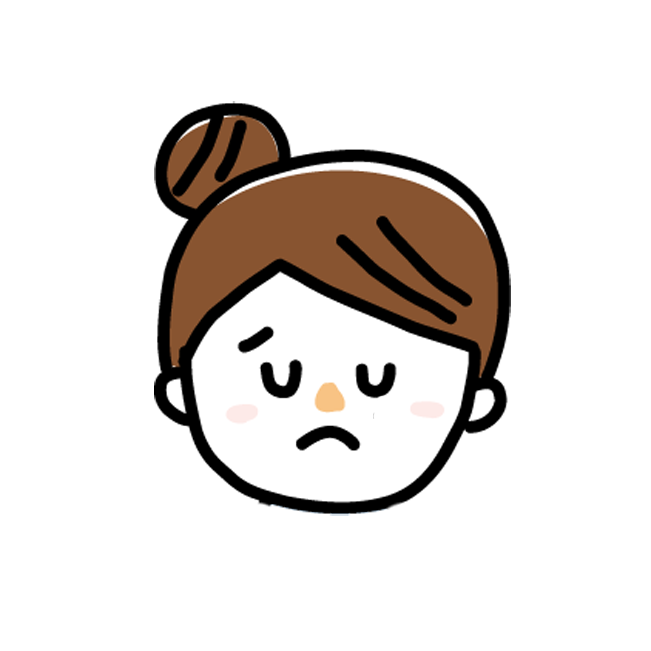 先生
先生そう言いたくなるぐらい、我慢してたのね
本人は「困っている」「我慢している」とは言っていませんが、
先生から注意されている = 状況的に困っている
嫌な気持ちを抱えている = 本人なりに我慢している
と理解することができます。
このときのポイントは、先生の独り言のように、心配するトーンで返すことです。
自閉スペクトラム症のある児童生徒は、自分が困っていること自体に気づきにくいことがあります。
そのため、先生から「困っている」「我慢している」と言われることで、
「えっ、自分は困っていたの?」「自分って、我慢していたのかも」と気づくきっかけになることがあります。
間違い指摘反射をおさえて
「困っていたんだね」「我慢していたんだね」と返す
「間違い指摘反射」はこちら
↓ ↓ ↓


5 何が正しいかではなく、損得を話題にする
「何が正しいか」を伝えることはもちろん大切です。
しかし、相手によっては、それを「価値観の押し付け」のように受け取られてしまうことがあります。
一方で、「何があなたにとって得か、損か」という説明は、
提案として受け取られやすく、合理的に感じやすいため、納得や行動につながりやすいと言われています。
例えば
- 「思いやりの言葉を使うと、あなたの良さがもっと伝わるよ。それって嬉しいよね」
- 「清潔にしていると、友だちに好かれやすいよ。休み時間がもっと楽しくなるね」
- 「宿題を提出すると、この科目は◯点も得できるよ。半分出せば◯点アップだね」
そもそも宿題はそういうものではない、という議論はここでは脇に置きます
これは、営業のセールストークにも似ています。
どれだけ「当たり前」のことだと感じていても、「〇〇すべき」「〇〇しなきゃダメ」とは言わず、
「あなたにとって得」「それはもったいない」と伝えるのです。
この伝え方には、次の利点があります。
- 相手を責めている印象を与えにくい
- 本人の自己決定を尊重できる
- 前向きな対話が生まれやすい
さらに、本人の「好きなこと・やりたいこと」と結びつけて損得を説明できると、
より説得力のある、魅力的なセールストークになります。
ただし、「私は損得では動きません」という価値観の相手には、逆効果になることがあります。
相手が納得しやすい説明方法を、相手に合わせて選ぶことが大切です。
「社会に必要なこと」
「あなたにプラスなこと」
あなたが児童生徒なら、
どっちを話題にしたいですか?

6 肯定的メッセージで足場をつくる
例えば
- 「このままでは、あなたが困るよ」
- 「これができるようになった方が、将来のためだよ」
- 「できるように練習してみませんか?」
これらは一見、前向きな助言に見えますが、実は背景に「ある前提」が隠れています。
それは・・・、「今のままではいけない」という小さな否定です。
今のままでよければ、そもそも助言する必要はありませんよね。
そのため、説得しようとして口調が強くなったり、同じ言葉を繰り返したりすると、
知らず知らずのうちに相手を否定してしまい、結果として自信や意欲を奪ってしまうことがあります。
助言には「今のままではいけない」
という小さな否定がある
そこで、助言するときには、次のような肯定的メッセージも添えることが大切です。
「〇〇できているね」「がんばっていたよね」「成長を感じるよ」
「助かっているよ」「それ、あなたの魅力だよね」「ありがとう」
「応援しているよ」「きっとできると思うよ」「いつでも頼ってほしい」
肯定的メッセージには、相手の自信・意欲を引き出し、行動につなげる「足場」をつくる効果があります。
自分の良い面を認めてくれる先生から、
「ここが成長すると、もっと良くなるよ」と言われることで、
「先生の気持ちに応えたい」
「自分自身に期待してもいいかもしれない」
という前向きな気持ちが生まれやすくなります。
本人の味方であり続ける姿勢で、そっと背中を押す存在になっていただけたらと思います。

まとめ
- 何度指導しても行動が変わらない、平気そうに見える、言い訳や開き直りがある。そんなとき「本人が困っていないことが問題」と感じるのは自然なことです
- 発達障害のある児童生徒には、「困っているけど、そう見えないだけ」「困っていても、自分ではどうにもできず、それが『普通』になっている」といったケースが少なくありません
- こうした状況への対応は簡単ではありませんが、対話を重ねつつ、肯定的メッセージで「あなたの味方だよ」という姿勢を示すことが、行動変容の足場づくりになります
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。
PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。
次回もどうぞお楽しみに。