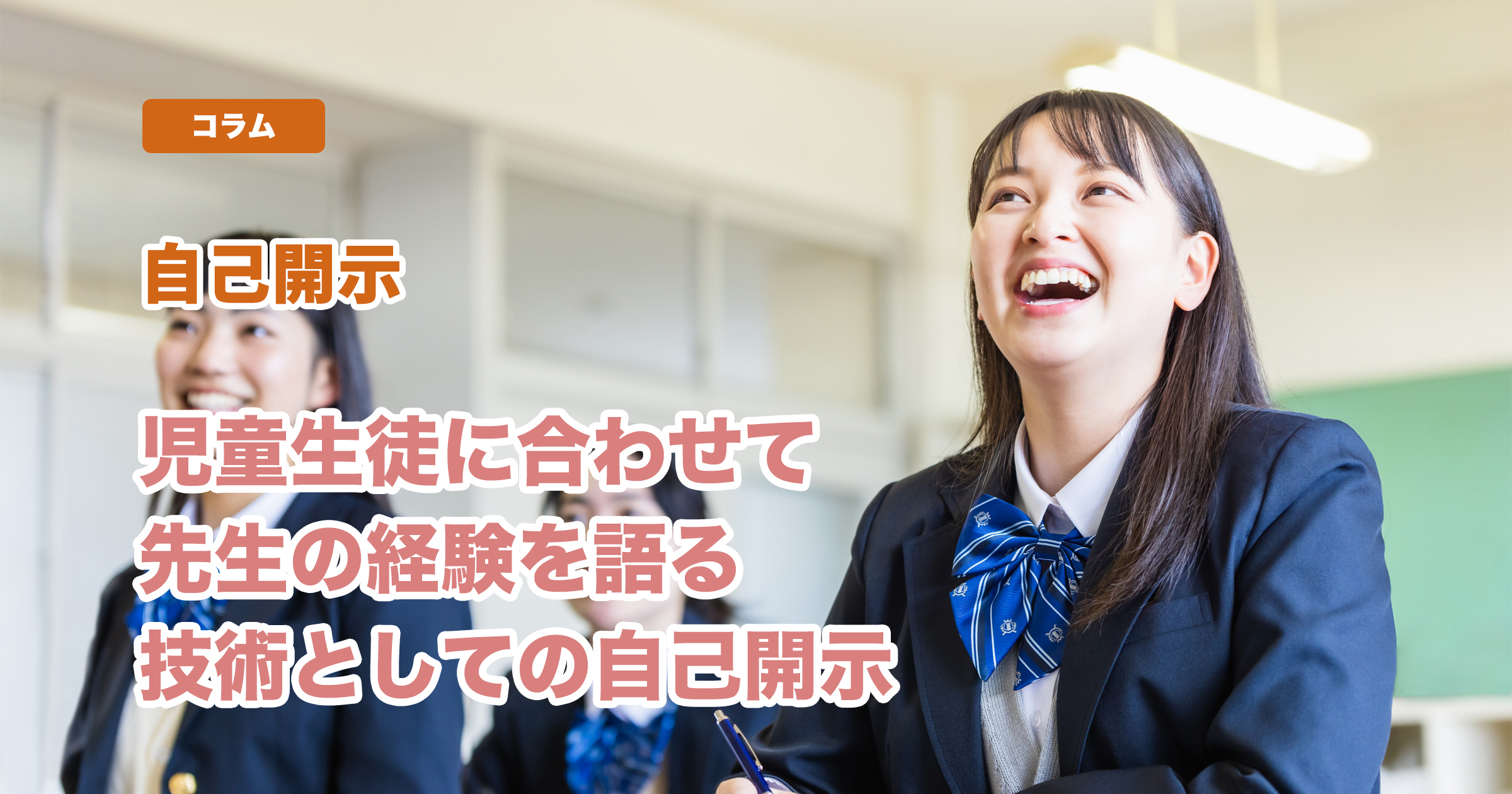自分の趣味や経験、気持ちを話すことで、相手と打ち解けたり、安心できる関係を築いたり・・・
私たちは日常の中で、さまざまな「自己開示」を行っています。
一方、教師が児童生徒に向けて行う自己開示は、日常的なものとは少し性質が異なります。
このコラムでは、「教師としての自己開示」に必要な視点を整理してみたいと思います。
内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。
このコラムは約3分で読めます。
1 自己開示とは
定義は、
自分自身をあらわにする行為であり、他者たちが知覚しうるように自身を示す行為
自分自身をあらわにする行為であり、他者たちが知覚しうるように自身を示す行為
Jourard, S. M.(1971)
例えば、次のような内容です。
- 好きなもの、趣味、休日の過ごし方、出身地
- 過去の経験、信念、苦手なこと・弱み
- 今、感じていること・考えていること
このように、自己開示の概念は広く、趣味や嗜好だけでなく「いま、ここ」の感情や考えなども含みます。
たとえば、「あなたを愛してる」は、人間にとって大切な自己開示です。
(1)一般的な自己開示
私たちは日常的に自己開示をしていますが、
その量や深さは、「相手との関係性」によって大きく異なります。
たとえば、私の場合、
美容室では、自分の職業や家族構成までは話しません。
一方で、友人には仕事の悩みや家族との関係、人生の目標など、より深い話をすることがあります。
親密な関係であるほど、自己開示の量は増え、その内容も深くなる傾向があります。
(2)返報性の原理
返報性(へんぽうせい)の原理とは、
自分が行った行為が、相手からも返ってくることです。
例えば
- 「いつも、ありがとう」と言うと、「こちらこそ」と返ってくる
- 「ふざけるな!」と言うと、「その言い方はひどい!」と返ってくる
- 横断歩道で車が止まると、歩行者は早く渡ろうとする
自己開示にもこの返報性が働きます。
自分が心を開けば、相手もまた心を開いてくれます。
そのやり取りを重ねることで、お互いの「不透明さ」が減り、関係はより親密になっていきます。
さらに、「普段は話さないようなことを自分に話してくれた」という体験は、
相手への好意や信頼感を高めることが、心理学の研究で示されています。
職員室での先生同士の会話でも、趣味や家族、過去の経験を共有することで、心理的な距離が縮まることがあると思います。
適度な自己開示は、良好な職場関係づくりにも役立つものです。

2 教師の自己開示
『生徒指導提要』では、次のように述べられています。
(3)児童生徒、保護者と教職員の相互理解の重要性
第1章 生徒指導の基礎 1.3生徒指導の方法 1.3.1児童生徒理解
的確な児童生徒理解を行うためには、児童生徒、保護者と教職員がお互いに理解を深めることが大切です。児童生徒や保護者が、教職員に対して、信頼感を抱かず、心を閉ざした状態では、広く深い児童生徒理解はできません。児童生徒や保護者に対して、教職員が積極的に、生徒指導の方針や意味などについて伝え、発信して、教職員や学校側の考えについての理解を図る必要があります。例えば、授業や行事等で教職員が自己開示をする、あるいは、定期的な学級・ホームルーム通信を発行することなどを通して、児童生徒や保護者に教職員や学校に対する理解を促進することが大切です。
黄マーカーは当Webサイトが引いたもの
よく言われるように、「児童生徒の心を開くためには、まずは教師が心を開くこと」が大切だとされています。
この考え方は非常に有効ですが、
一方で「自己開示しなければならない」と感じ、居心地の悪さや負担を覚える教師も少なくありません。
それは、本来は個人的で自発的な行為である自己開示が、
教師という専門職に求められる”スキル”として扱われているからです。
自己開示は、あくまで無理のない範囲で、自然な形で行うことが大切です。
その前提のもとで、「効果的な自己開示」とは何かを、一緒に考えていきましょう。
言いたくないことを質問されたら
「事務所NG」と答えちゃう
(参考)教師の自己開示に関する研究
次のような傾向が報告されています。
- 「特別の教科 道徳」や「学級活動」の時間に、自己開示が多い
- 自己開示は、1学期前期に多い
- 児童生徒の変容を意識した、意図的な自己開示が多い
- 高校生が好意的に感じるのは「学生時代の思い出」「社会の出来事」など
逆に、「生徒への立腹」「経歴の自慢話」「学級全体の批判」などは好意的に受け取られにくい - 自己開示の多い教師は、児童生徒との心理的距離が近い
1〜3(木村,2009)、 4(横島・吉田・小熊,1997)、5(山口,1994)
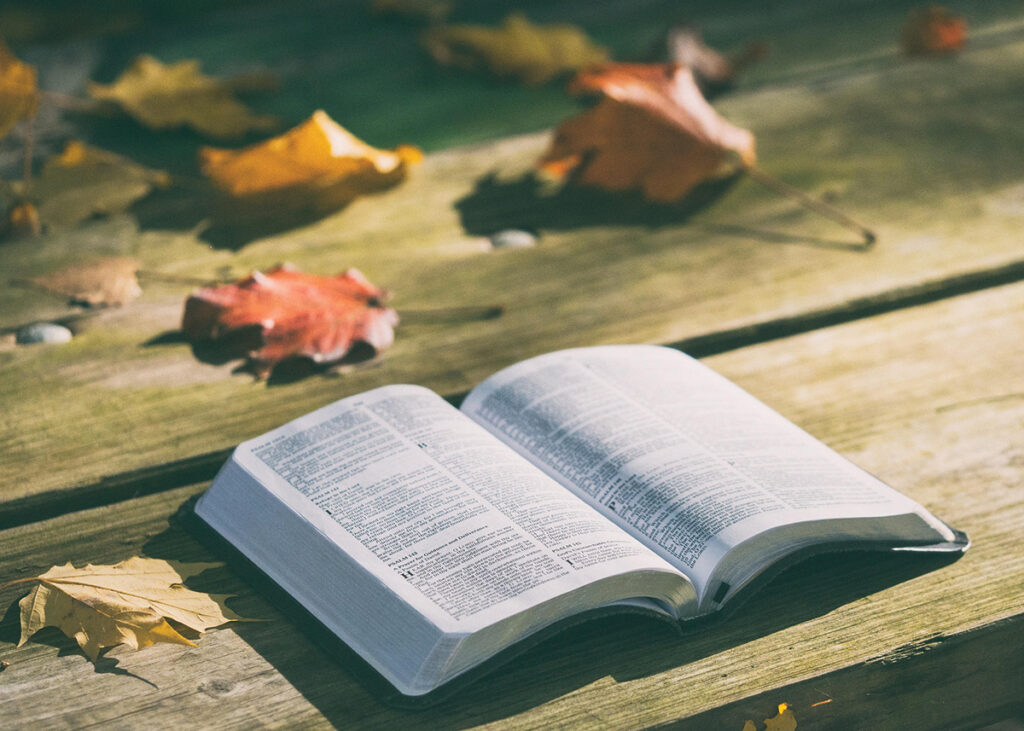
3 効果的な自己開示(集団)
学級などの「集団」に対して教師が自己開示する際には、次の3つのポイントがあります。
(1)対話を生み出す
例えば
 先生
先生昨日の夜、ジブリの映画が放送されていたよね
おもしろかった〜
観た人はいますか?
このような自己開示をすると、児童生徒から
「先生、ジブリ映画が好きなんですか?」
「一番好きな作品は何ですか?」
といった反応が返ってくることがあります。
また、休み時間に「先生、トトロは好きですか?」と声をかけてくれる児童生徒もいるかもしれません。
このように、教師の自己開示をきっかけに対話が生まれ、心理的な距離が縮まる。
これが、効果的な自己開示のひとつの形です。
一方で
 先生
先生昨日の夜、家族でレストランに行ったんだけど、注文した料理と違うものが出てきて、本当に腹が立ったんだ
タブレットで注文しているのに、どうしてそんなミスが起きるのか、不思議だと思わない?
そのあと、店員が言った言葉が衝撃で・・・
このような自己開示は、先生が一方的に話す形になりやすく、児童生徒は聞き手に回ってしまいます。
その結果、対話が生まれにくく、かえって距離を感じさせてしまうことがあります。
効果的な自己開示とは、児童生徒とのやり取りを引き出す「呼び水」になるものです。
自己開示も
一方通行は、事故に注意です
(2)教師の印象を調整する
例えば
「厳しい印象」の先生が、次のような話をしたら・・・
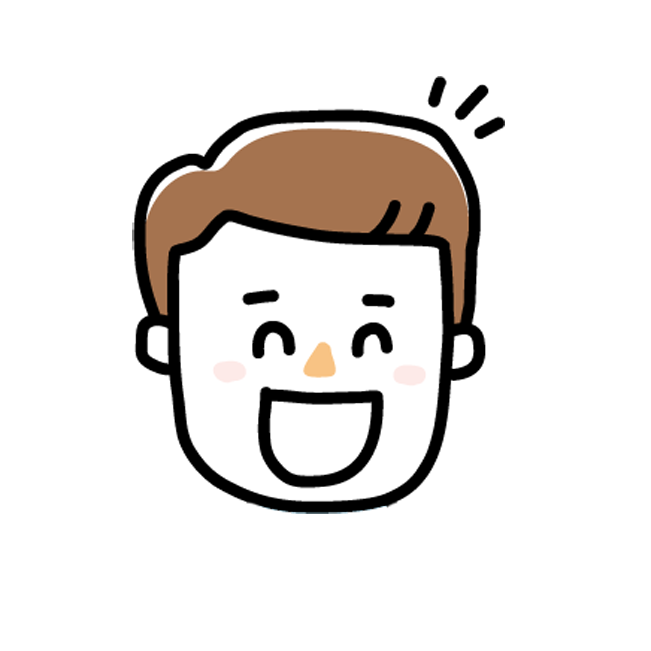 先生
先生うちには猫がいるんだけど、本当にかわいくて、
つい写真をたくさん撮っちゃうんだ
疲れたときには、その写真を見て癒されるんだけど、
早く家に帰って会いたくなっちゃうんだよね〜
児童生徒は「先生にもそんな一面があるんだ」「実は優しい先生なのかも」と感じるかもしれません。
また、「しっかりした印象」の先生が、次のような話をしたら・・・
 先生
先生今朝、洗顔しようとして間違えて歯磨き粉を顔につけちゃってね
朝から目がヒリヒリして大変だったんだよ
いまだに息をするたびにミントの香りがするの(笑)
児童生徒は「先生も失敗することがあるんだ」「なんだか親近感がわく」と感じるかもしれません。
このように自己開示には、教師の印象をやわらげ、児童生徒との心理的距離を縮める効果があります。
特に、「失敗談」や「弱みの共有」は信頼関係を深め、
児童生徒にとって「相談しやすい先生」という印象を形成するうえでも有効です。
「情熱大陸」「アナザースカイ」も
苦労したエピソードを入れている
(3)教師がモデルになる
例えば
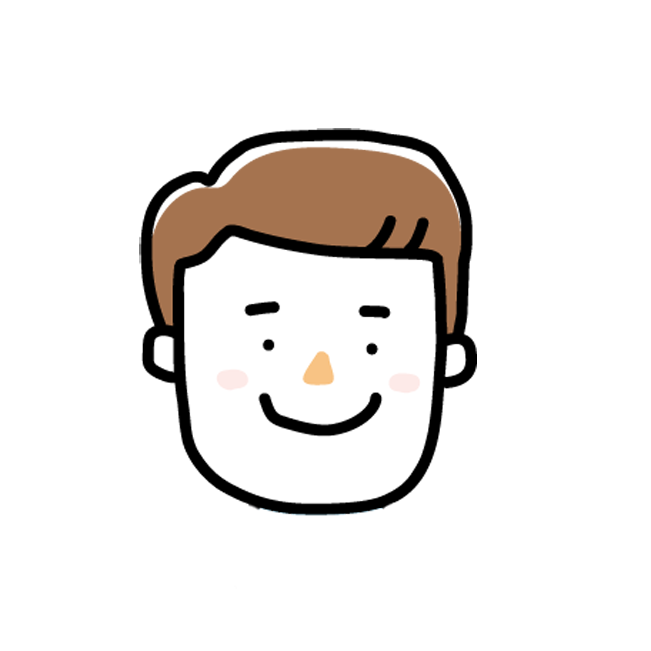 先生
先生チャレンジすることって大切だよね
私も今年からランニングを始めたんだ
いつかフルマラソンを走ってみたいと思っているよ
このような自己開示を聞くと、児童生徒は、
「先生も新しいことにチャレンジしている」「言葉だけじゃなくて行動している」と感じるかもしれません。
ほかの例では
 先生
先生私は中学生のとき、不登校の時期があったの
当時は、どうして学校に行きたくないのか、自分でもよく分からなかったんだ
児童生徒は、「先生にもつらい時期があったんだ」「それを乗り越えてきた人なんだ」と感じ、
勇気づけられるかもしれません。
児童生徒は、「先生にもつらい時期があったんだ」「それを乗り越えてきた人なんだ」と感じ、勇気づけられるかもしれません。
このような自己開示は、児童生徒にとって「一つのモデル」となる可能性をもっています。
実際、自分の経験を「児童生徒の考えを深める材料」として語る教師は少なくありません。
特に、児童生徒との共通点が多い内容であるほど、より強い影響を与えると考えられます。
ただし、話が長くなりすぎると、自己開示が「自慢話」や「教師自身のカタルシス」になってしまうおそれがあります。
「児童生徒に何を感じてほしいのか」という目的を明確にし、簡潔に伝えることが大切です。
このモデルは
ランウェイを歩きません

4 効果的な自己開示(個人)
個別面談など、「個人」に対して教師が自己開示する際には、次の2つのポイントがあります。
(1)会話の主体を奪わない
例えば
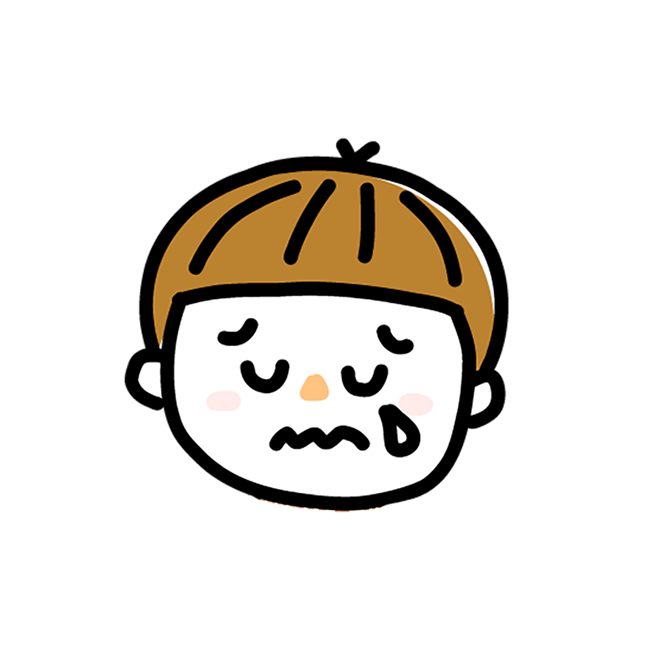 児童生徒
児童生徒SNSで自分の悪口を言われていたなんて…
もう誰も信用できません
 先生
先生そんな気持ちになるよね…
私も昔、親友から裏切られたことがあって、
誰も信用できなくなった時期があるよ
 児童生徒
児童生徒…親友から裏切られたんですか?
先生は、共感を示そうとして、自分の経験を話しましたが、
結果的に会話の主体を先生が奪ってしまい、児童生徒は自分の気持ちを語る機会を失ってしまいました。
教師が「児童生徒と似た経験」を自己開示すること自体は、
親近感や信頼感を生むきっかけとなり、決して悪いことではありません。
ただし、タイミング・内容・話し方に配慮が欠けると、
児童生徒に「話を奪われた」と感じさせてしまうことがあります。
先ほどの例でいえば、児童生徒の気持ちを十分に聴いたあとで、
「私は学生時代に似たような経験があって、気持ちが落ち着くまで少し時間がかかったよ」
といったように、表現を少し柔らかくすれば、
自然に会話の流れを保ちながら、児童生徒が受け取りやすい自己開示になったと思います。
共通するものを見つけても
自分のターンまで黙っている
(トランプにもそんなゲームがありますね)
(2)話を聴いて感じたことを伝える
例えば
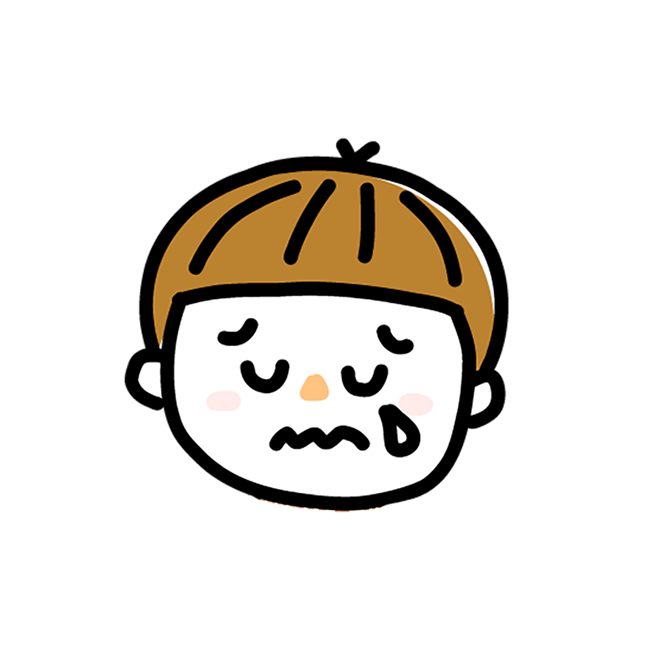 児童生徒
児童生徒SNSで自分の悪口を言われていたなんて…
もう誰も信用できません
 先生
先生それぐらいショックな出来事だよね
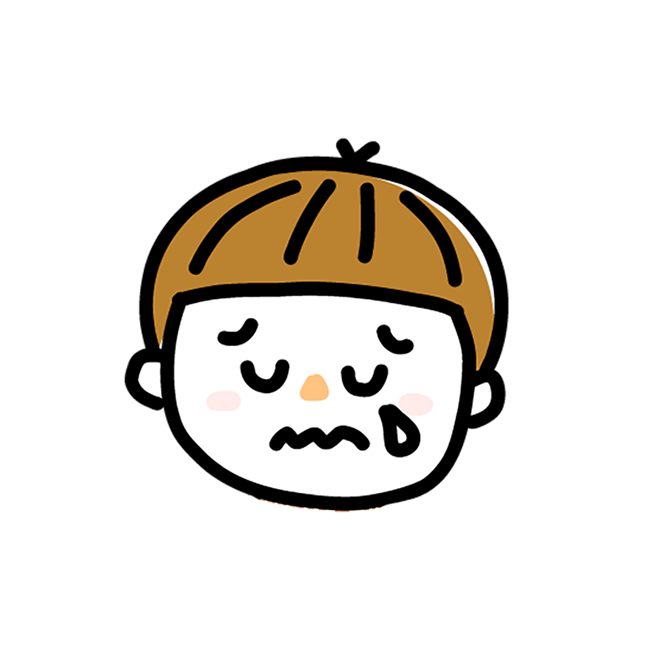 児童生徒
児童生徒(涙)すごくショックでした
学校では普通に話していたのに、
あんなふうに思われていたなんて…
 先生
先生全く想像してなかった…
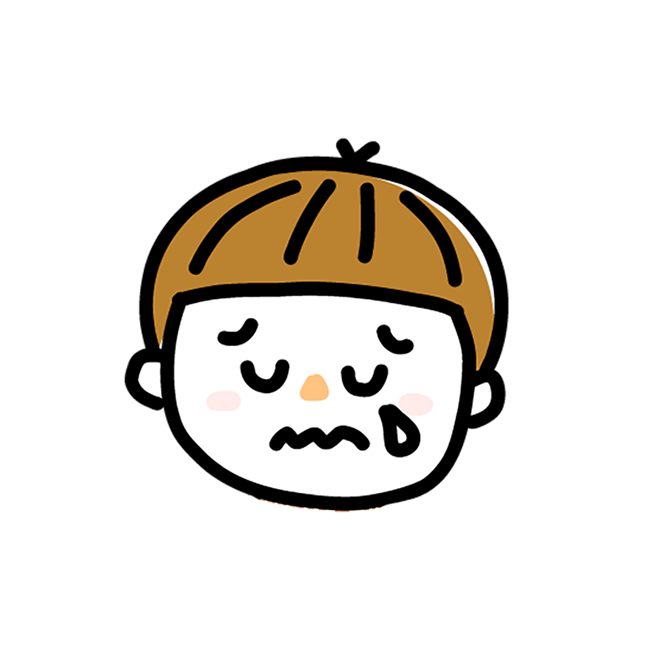 児童生徒
児童生徒そうなんです
少しでも嫌われているような感じがあれば、
「やっぱり」と思えたかもしれないけど、
全然そんな様子はありませんでした…
 先生
先生あまりに普段の様子と違っていたんだね…
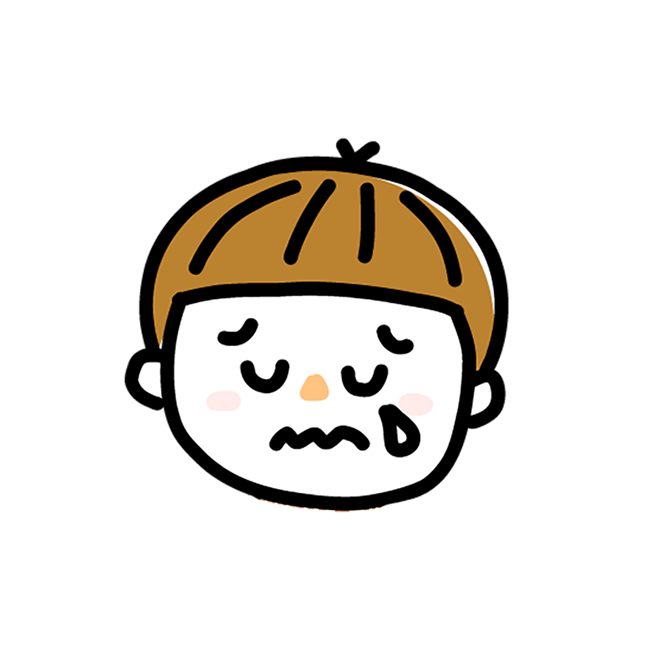 児童生徒
児童生徒はい…
どんな顔で会ったらいいのか分かりません
 先生
先生そうだよね…。
私は話を聴いていて、どれほどショックが大きく、傷つくものだっただろうかと、感じているよ
それと、それほどつらい気持ちを、よく勇気を出して話してくれたと思うよ
先生は「過去の経験」ではなく、「今、感じたこと」を自己開示しています。
児童生徒の話を聴いて心に浮かんだ思いを言葉にしており、会話の主体はあくまで児童生徒のままです。
このような自己開示は、落ち着いた口調で素直に気持ちを表現するモデルにもなり、
返報性の原理によって、児童生徒の感情表現を促すことにもつながります。
そして、教師と児童生徒との心理的な距離を縮め、信頼感を深めるかかわり方となります。
また、このような教師の言葉が、児童生徒にとって心の支えになることも少なくありません。
「いま・ここ」の素直な気持ちを伝えるから、人の心は動く

まとめ
- 自己開示は、教師自身に負担のない範囲で、自然に行うことが大切である
- 集団に自己開示するときのポイントは、「対話を生み出す」「失敗談や弱みを話す」「短く伝える」
- 個人に自己開示するときのポイントは、「話を奪わない」「いま・ここの気持ちを伝える」
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。
PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。
次回もどうぞお楽しみに。