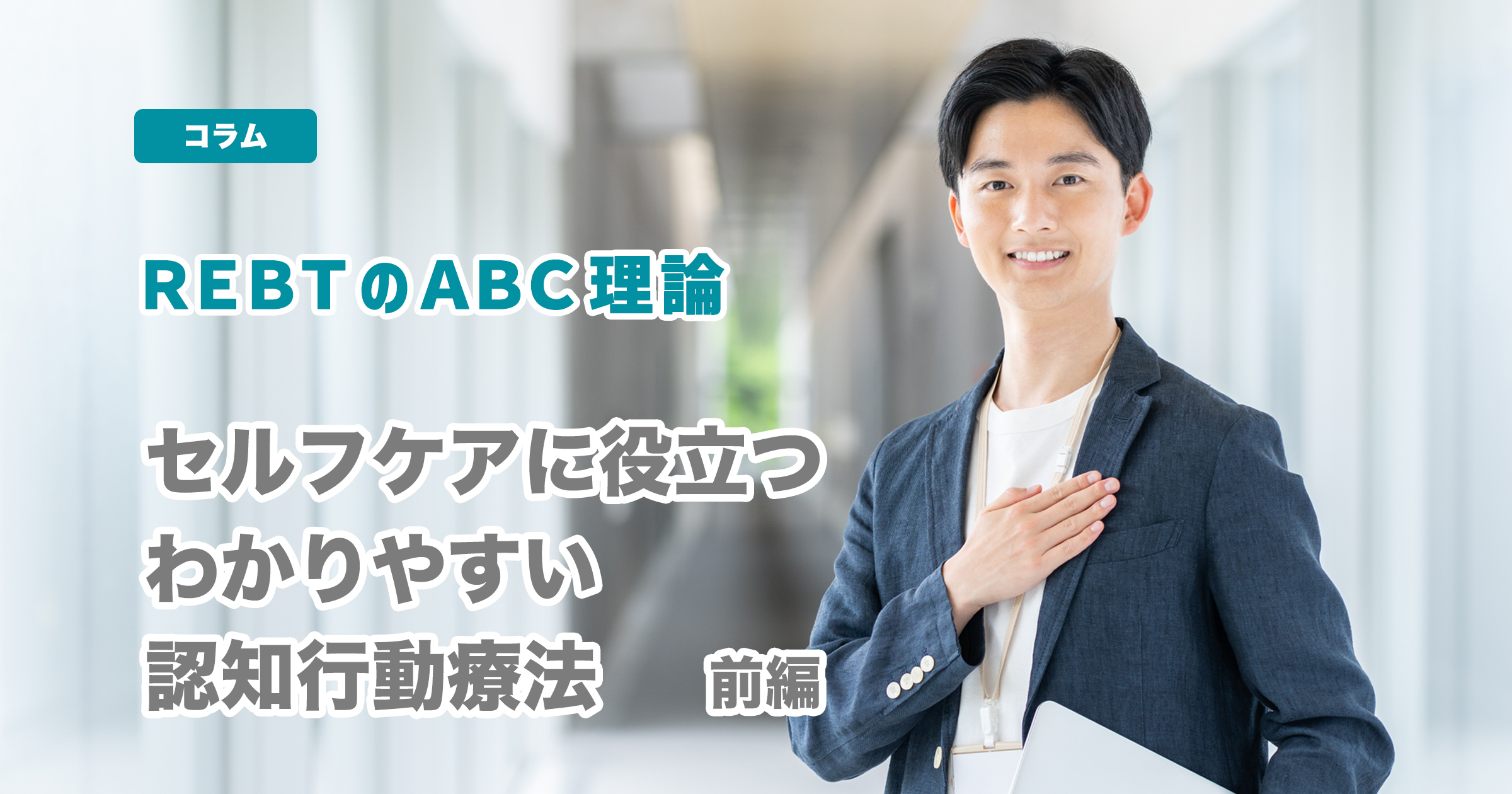「教師は、きちんと指導しなければならない。」
「児童生徒は、教師の指導を素直に聞くべきだ。」
多くの教職員が、「そう通り」とうなずく言葉です。
しかし、こうした考えを強く持ちすぎると、心の健康を崩してしまうことがあります。
このコラムでは、教職員が「自分自身のセラピスト」になる方法について紹介します。
内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。
このコラムは約3分で読めます。
1 ABC理論
ABC理論は、認知行動療法の一つであるREBTという心理療法の基本概念です。
「ABC」が意味するものは次の通りです。
A: Activating Event 出来事
B: Belief(ビリーフ) 考え・信念
C: Consequence 結果(感情など)
では、次の先生の事例で考えてみましょう。

ある児童生徒への指導が、うまくいきません。
自分に原因があるように感じ、憂うつで教室に向かう足も重くなっています。
恥ずかしくて誰にも相談できず、周りからの協力も得られません。
ある児童生徒への指導が、うまくいきません。
自分に原因があるように感じ、憂うつで教室に向かう足も重くなっています。
恥ずかしくて誰にも相談できず、周りからの協力も得られません。
このような状態は、次のように誤って捉えられがちです。
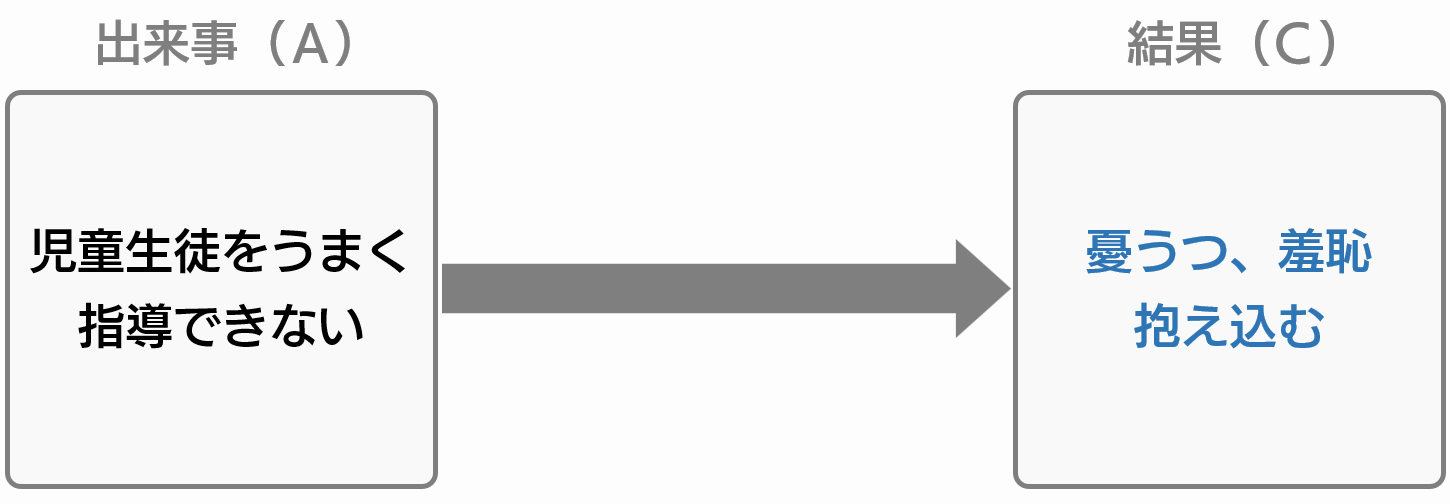
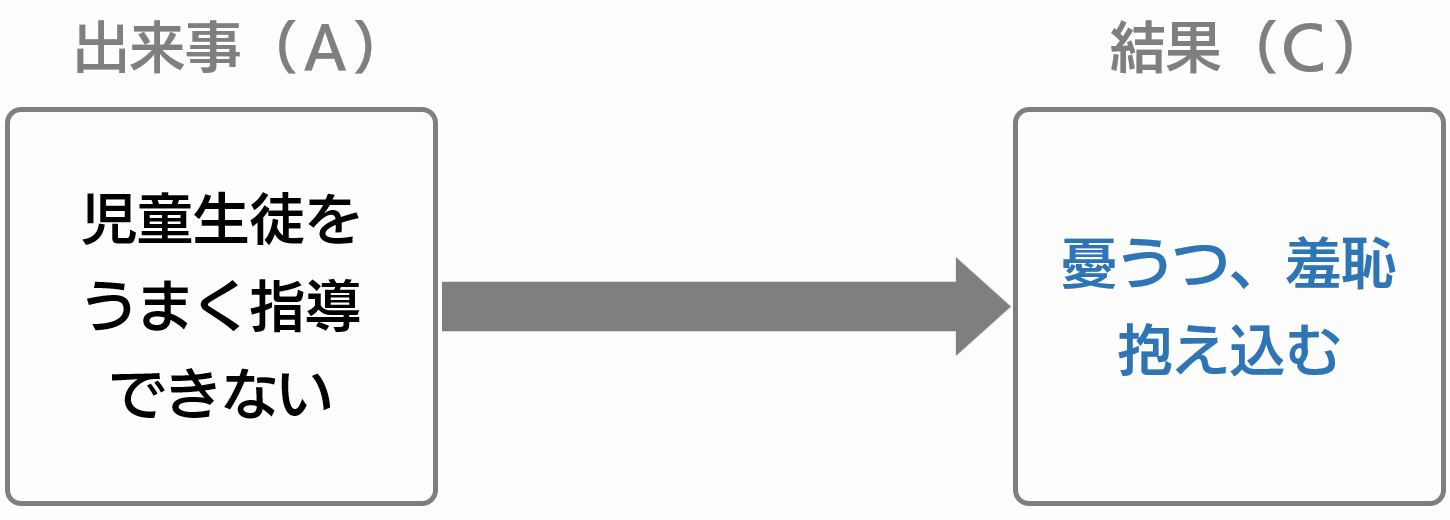
出来事(A)があったから、結果(C)になった
出来事(A)があったから
結果(C)になった
しかし実際には、同じ出来事(A)に直面しても、すべての教師が同じ結果(C)になるわけではありません。
例えば、「自分に怒りを感じる」「信頼できる人に相談する」「教育の奥深さに興味を持つ」など、結果(C)はさまざまです。
この違いを生み出すのが、 考え・信念(B)です。
今回の先生は、次のように考えていました。
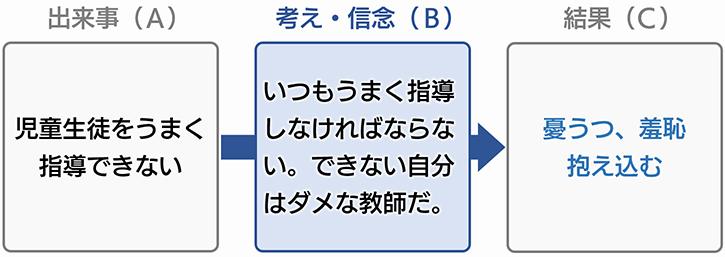
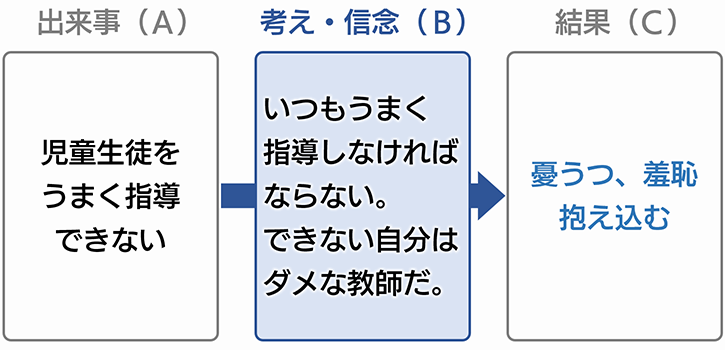
出来事(A)に対して
ある考え・信念(B)を持ったから、結果(C)になった
出来事(A)に対して
ある考え・信念(B)を持ったから
結果(C)になった
このように考えたら、憂うつや羞恥を感じるのも無理はありません。
結果(C)に苦しんでいるとき、その原因の大半は、出来事(A)ではなく、考え・信念(B)にあります。
そこで、この先生は、考え・信念(B)を次のように変えてみました。
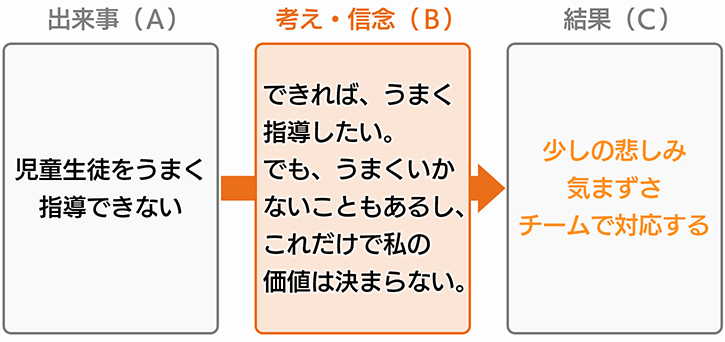
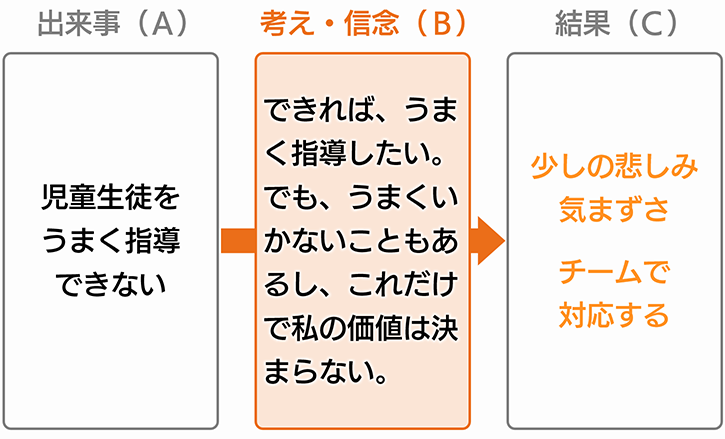
出来事(A)が変わらなくても
考え・信念(B)を変えることで、結果(C)は変えられる
出来事(A)が変わらなくても
考え・信念(B)を変えることで
結果(C)は変えられる
結果(C)も変わりました。
この先生は、新しい考え・信念(B)を頭の中でつぶやくだけで、気持ちが少し楽になったようです。
また、結果(C)が変わったことで、「出来事(A)を変えるための行動」も取りやすくなりました。

人を悩ませるのは出来事そのものではなく
その出来事に対する受け取り方である
人を悩ませるのは出来事そのものではなく、その出来事に対する受け取り方である
2 ビリーフ(考え)に注目する
考え・信念(B)には、次の2種類があります。
- イラショナル・ビリーフ
(非合理的な考え) - ラショナル・ビリーフ
(合理的な考え)
「非合理的」「合理的」の解説は、後編のコラムに回しますが、
ここでは、次の法則をざっくりと理解してください。
イラショナル・ビリーフは、「不健康な感情」や「非機能的な行動」につながり、
ラショナル・ビリーフは、「健康な感情」や「機能的な行動」につながる。
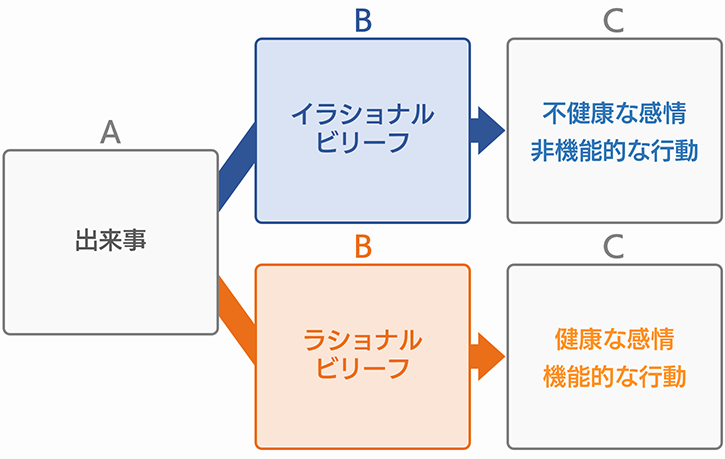
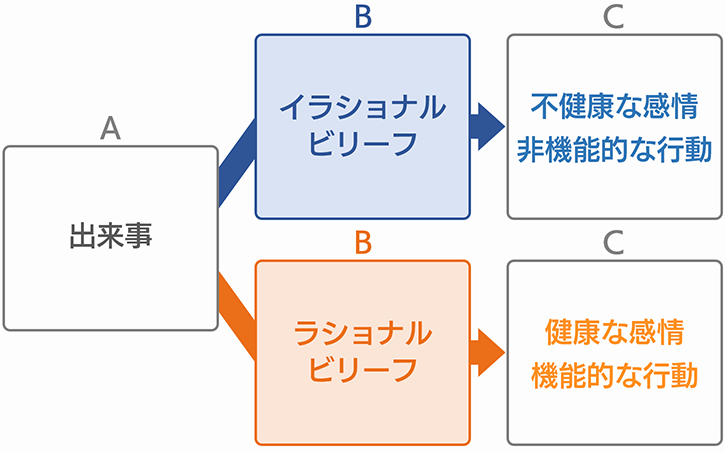
もっとシンプルに言うと、
イラショナル・ビリーフは「不健康」
ラショナル・ビリーフは「健康」です。
では、イラショナル・ビリーフについて、詳しく見ていきましょう。

3 イラショナル・ビリーフ
イラショナル・ビリーフは、次のような形になっています。
「〇〇でなければならない。そうでなければ〇〇だ。」
(1)「〇〇でなければならない」
「ねばならない思考」「べき思考」と呼ばれるものです。
例えば
- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。」
- 「児童生徒は、ルールを守るべきである。」
- 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。」
これだけ見ると、「まぁ、そうかな」とうなずく先生も多いと思います。
ただ、もしあなたが「当たり前でしょう!」「そうじゃないわけがない」と強く信じているのであれば、
「そうでなければ〇〇だ」という考えも持っているのではないでしょうか。
(2)「そうでなければ〇〇だ」
極端な評価を表す言葉です。
例えば
- 恐ろしいビリーフ
- 「私は、すべての児童生徒から好かれなければならない。そうでなければ恐ろしい。」
- 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。そんな教師は最悪だ。」
- 耐えられないビリーフ
- 「管理職は、リーダーシップを発揮しなければならない。そうでなければ耐えられない。」
- 「保護者は、学校の教育に協力的であるべきだ。そうでなければ、やってられない。」
- 価値がないビリーフ
- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。そうでなければ、価値がない。」
- 「児童生徒は、ルールを守らなければならない。そうでなければダメな人間だ。」
自分の中に「ねばならない」を見つけたら
「そうでなければ・・・?」と自問してみましょう
自分の中に「ねばならない」を
見つけたら
「そうでなければ・・・?」と
自問してみましょう
現実は、常に良い仕事ができるわけがなく、ルールを守れない児童生徒や、時に児童生徒を傷つける先生も存在します。
そのため、イラショナル・ビリーフ(B)を持っていると、
結果(C)で、不健康な感情や強いストレスを抱えてしまいます。

では、どうしたらよいのでしょうか?
それは、
イラショナル・ビリーフを
ラショナル・ビリーフに置き換える
ビリーフ(B)を変えることで、結果(C)が変わります。
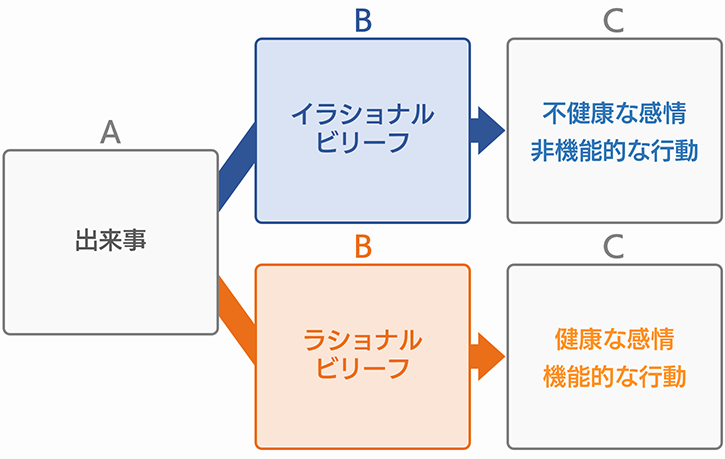
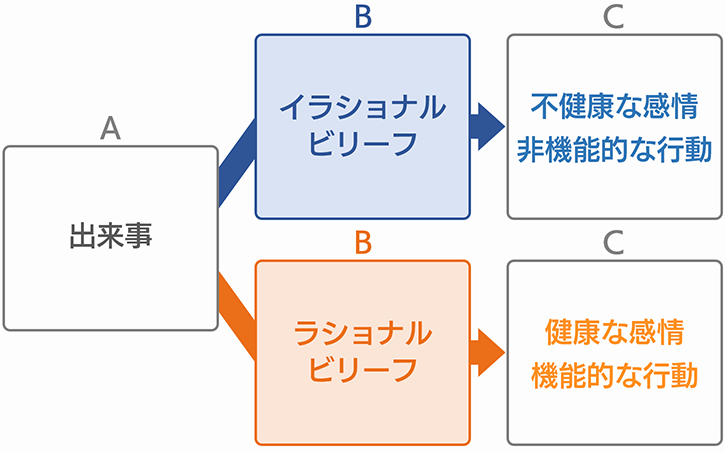
次は、ラショナル・ビリーフについて見ていきましょう。
4 ラショナル・ビリーフ
ラショナル・ビリーフは、次のように作ります。
「〇〇であってほしいが、そうならないこともある。
〇〇でないのは嫌だが、最悪ではない。」
(1)「〇〇であってほしいが、そうならないこともある」
「ねばならない」を、次のように変更します。
「〇〇であってほしいが、そうならないこともある。」
「〇〇だといいなと思うが、〇〇でないこともある。」
例えば
- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。」
「私は、いつも良い仕事をしたいが、そうできないこともある。」 - 「管理職は、リーダーシップを発揮しなければならない。」
「管理職には、リーダーシップを発揮してもらいたいが、そうでないこともある。」 - 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。」
「教師は、児童生徒を傷つけない人であってほしい。しかし、そうでない教師もいる。」
現実的な文章に変わったと思いませんか?
現実の世界は複雑なので、文章も長くなります。
さらに次の文章も付け加えてみましょう。
(2)「〇〇でないのは嫌だが、最悪ではない」
「終わりだ」「耐えられない」を、次のように変更します。
「〇〇でないことは悪いことだが、終わりではない。」
「〇〇でないことは嫌だが、耐えられないほどではない。」
例えば
- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。そうでなければ、価値がない。」
「私は、いつも良い仕事をしたいが、そうできないこともある。
それは残念なことだが、私の価値とは関係がない。」 - 「管理職は、リーダーシップを発揮しなければならない。そうでなければ耐えられない。」
「管理職には、リーダーシップを発揮してもらいたいが、そうでないこともある。
そのような管理職に不満はあるが、耐えられないほどではない。」 - 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。そんな教師は最悪だ。」
「教師は、児童生徒を傷つけない人であってほしい。しかし、そうでない教師もいる。
それは大きな課題だが、その教師にも良い面はあり、それだけで最悪とは言えない。」
- 「私は、いつも良い仕事をしなければならない。そうでなければ、価値がない。」
「私は、いつも良い仕事をしたいが、そうできないこともある。それは残念なことだが、私の価値とは関係がない。」 - 「管理職は、リーダーシップを発揮しなければならない。そうでなければ耐えられない。」
「管理職には、リーダーシップを発揮してもらいたいが、そうでないこともある。そのような管理職に不満はあるが、耐えられないほどではない。」 - 「教師は、児童生徒を傷つけるような人間であってはならない。そんな教師は最悪だ。」
「教師は、児童生徒を傷つけない人であってほしい。しかし、そうでない教師もいる。それは大きな課題だが、その教師にも良い面はあり、それだけで最悪とは言えない。」
「ではない」「とは言えない」で、極端な評価を否定するのがポイントです。
「過度な要求」や「極端な評価」に気づいて
ほどほどに調整する
前編のまとめとして、ワークで練習してみましょう!

5 ワークで練習してみよう!
次のイラショナル・ビリーフを、ラショナル・ビリーフに言い換えてみましょう。
- イラショナル・ビリーフ
「私は、すべての児童生徒から好かれなければならない。そうでなければ恐ろしい。」
解答はこちら
ラショナル・ビリーフ
「私は、児童生徒から好かれたいが、好かれないこともある。それは残念なことだが、恐れることではない。」
- イラショナル・ビリーフ
「児童生徒は、ルールを守らなければならない。そうでなければダメな人間だ。」
解答はこちら
ラショナル・ビリーフ
「児童生徒には、ルールを守ってほしいが、守れないこともある。それは学びの途中であり、その児童生徒の価値とは関係がない。」
- イラショナル・ビリーフ
「保護者は、学校の教育に協力的であるべきだ。そうでなければ、やってられない。」
解答はこちら
ラショナル・ビリーフ
「保護者が、学校の教育に協力的だといいなと思うが、そうでないこともある。思うようにいかないこともあるが、やっていけないほどではない。」

まとめ
- 出来事(A)が変わらなくても、考え・信念(B)を変えることで、結果(C)は変わる。
- 「ねばならない」「べきである」「そうでなければ〇〇だ」といった考えは、精神的健康を損なう原因になる。
- 考え・信念(B)を置き換えることで、結果(C)は健康的・機能的になり、精神的健康の向上につながる。
「でも、考えを変えるのは簡単じゃない」と感じている方は、後編をお楽しみに!
後編はこちら
↓ ↓ ↓
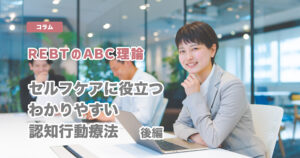
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。
PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。
次回もどうぞお楽しみに。