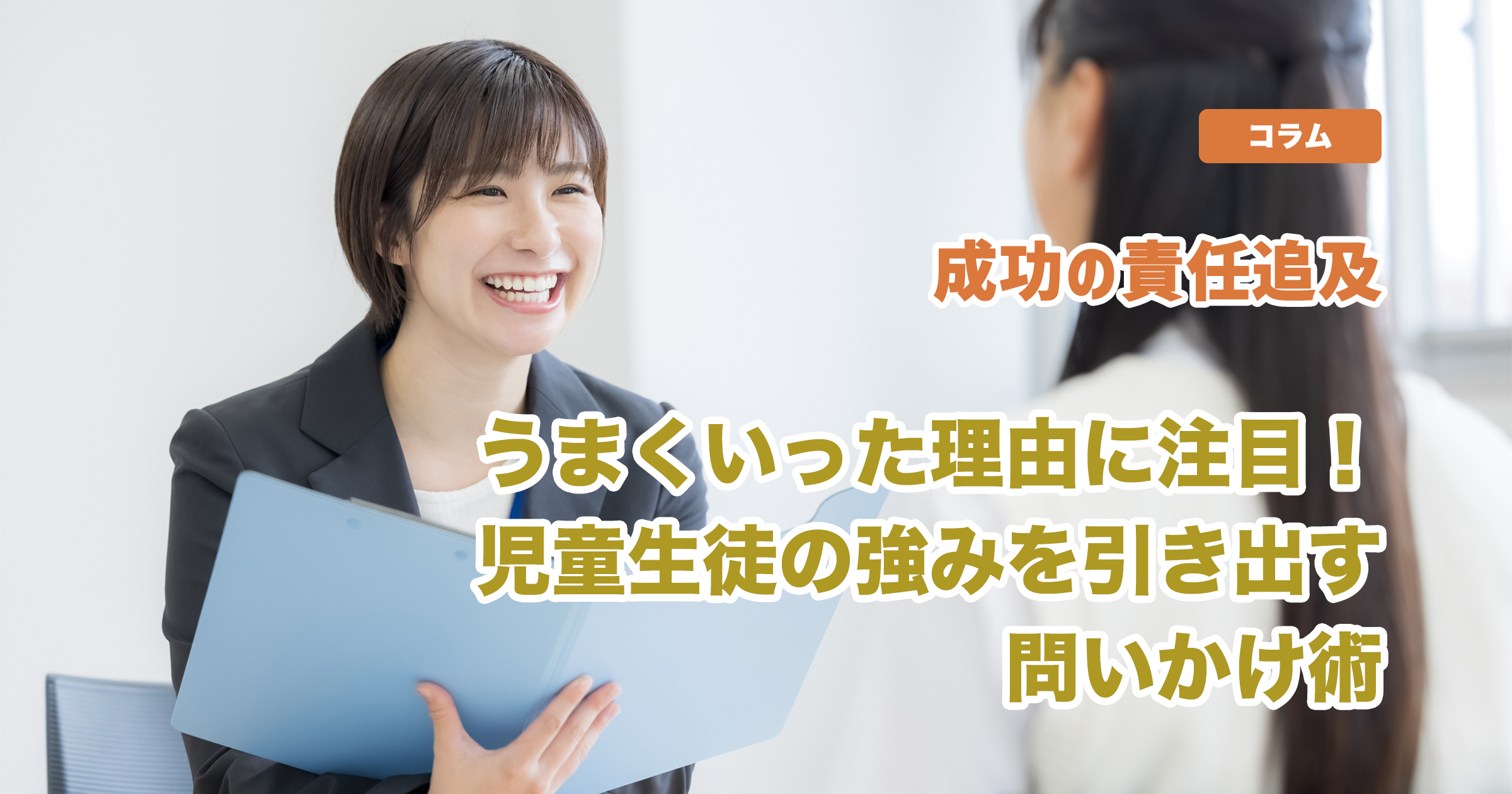「失敗の責任追及」ではなく、「成功の責任追及」です。
「うまくいったのに、なぜ責任を追及するの?」と、不思議に思われるかもしれません。
でも、このコラムを読み終えるころには、「成功のときこそ、責任追及しよう!」と思っていただけるはずです。
このコラムでは、児童生徒の強みに光を当て、その力を伸ばす問いかけ術を、具体例とともに紹介します。
内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。
このコラムは約3分で読めます。
1 成功の責任追及とは
解決志向アプローチの技法の一つです。
その意味は文字通り、
うまくいったことに対して、その理由を問いかけること
うまくいったことに対して
その理由を問いかけること
先生同士の会話では、
例1 授業が上手な先生に
「とても授業が上手ですよね!どんな工夫をされているんですか?」
例2 机の上がきれいな先生に
「いつも整理されていますよね。どうやって維持しているんですか?」
「どうやったの?」「どんな工夫を?」と、うまくいった理由を問いかけます。
ヒーローインタビューのようなイメージです。
ここでいう「成功」は、大きな成果に限りません。
うまくいったこと以外にも、
- 問題が起こらなかったこと
- ちょっとましだったこと
- たまたま起きたように思える良い変化
これらに対しても、「どうやったの?」「どんな工夫を?」と問いかけます。
先生同士の会話では、
例3 不登校傾向の児童生徒の様子について
「〇〇さん、教室には戻れてないけど、表情が明るくなりましたよね!どんなふうに接しているんですか?」
例4 児童生徒のトラブルの減少について
「最近、先生の学級は少し落ち着きましたよね!どんな指導をされたのですか?」
これらは、「問題」の中にある「小さな良い変化」に注目した問いかけです。
こうした質問を受けた先生は、自分の対応を振り返ります。
その振り返りから、自分の「できていること」「もっているもの」に気づくことができるかもしれません。
例えば
できていること
例3「〇〇さんの好きな話題で楽しく会話できている」
例4「大変なことは多いけど、粘り強く話を聴いて、指導している」
もっているもの
例3「児童生徒を笑顔にするのが得意なのかも(強み)」
例4「話を聴くことを大切にしている(価値観)」
エネルギーが高まり、自信を持つきっかけになるような会話です。
人は「うまくいった理由」を問われると
自分の「できていること」「もっているもの」を探し始める
人は「うまくいった理由」を
問われると
自分の「できていること」
「もっているもの」を探し始める

「解決志向アプローチ」はこちら
↓ ↓ ↓

2 学校での活用例
具体例1 うまくいったこと①
 Aさん
Aさん先生~
成績が上がりました!すごくないですか?
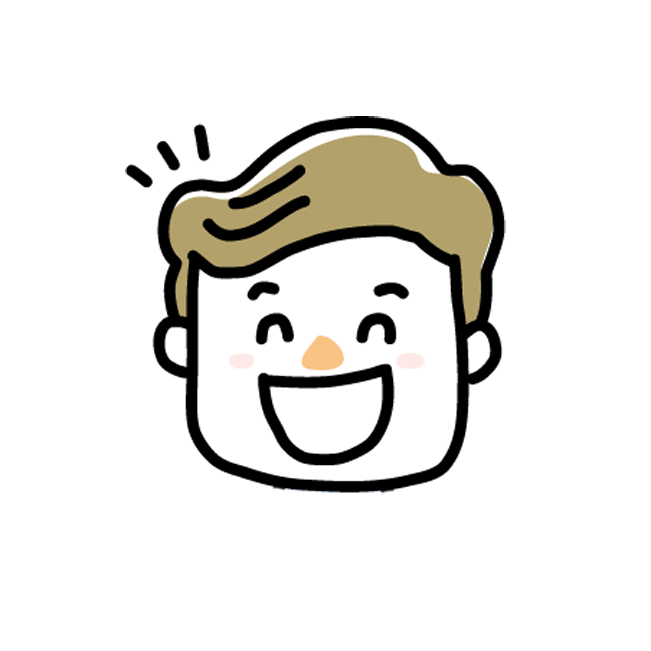 先生
先生すごいよ!がんばったね!
 Aさん
Aさんですよね!
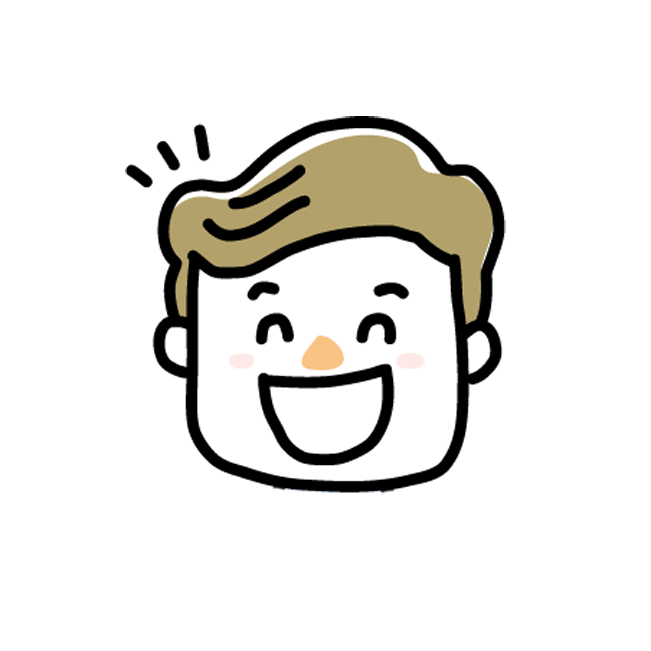 先生
先生うんうん!
それで、どうやって成績を上げたの?
(成功の責任追及)
 Aさん
Aさん・・・
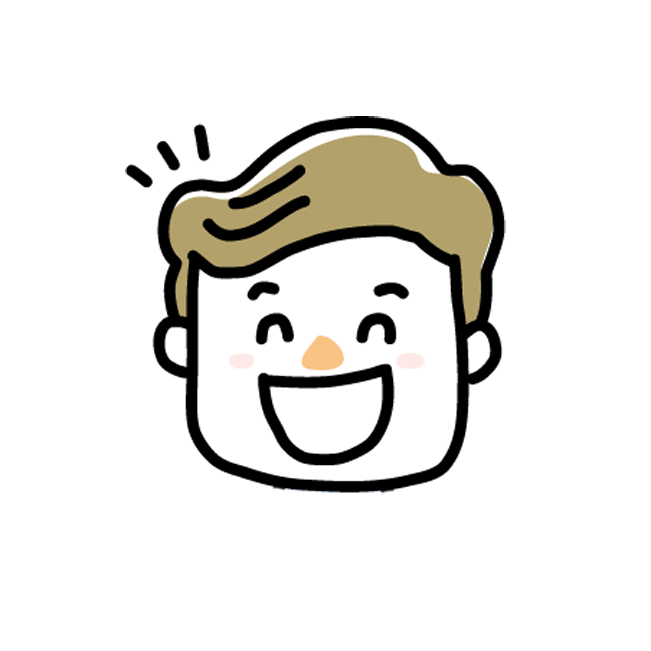 先生
先生何か変えたことがあるんじゃない?
(成功の責任追及)
 Aさん
Aさん変えたこと?
あ、少し勉強時間が増えたかも・・・
ゲームをあまりしなくなったから
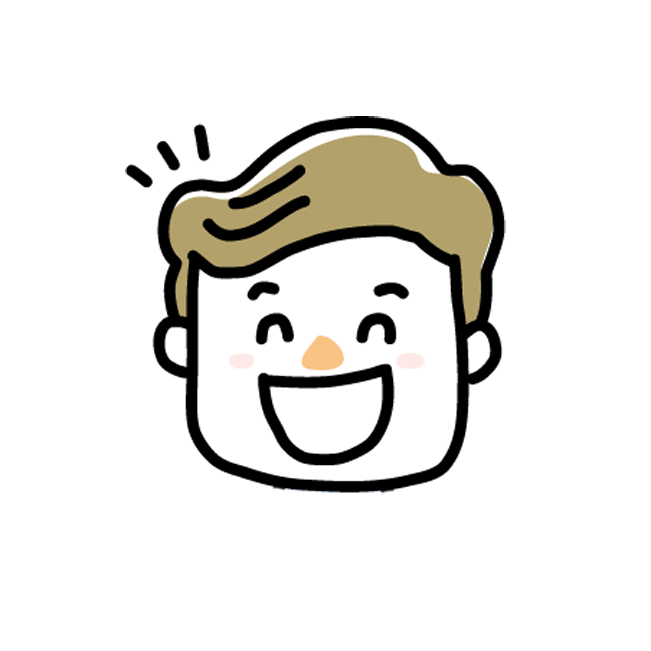 先生
先生そう〜、たいしたもんだよ!
- Aさんは、「成績が上がった理由」を振り返り、自分の「できていること」に気づいています
- 先生は結果だけでなく、その過程をAさんの努力として認めています
「ほめ言葉 + 成功の責任追及」で
うまくいった理由への気づきを促す

具体例2 うまくいったこと②
 先生
先生Bさんは、いつも笑顔が素敵だよね〜
 Bさん
Bさんそうですか?
 先生
先生一緒にいると楽しくなるよ
どうしたらそんなふうにできるの?
(成功の責任追及)
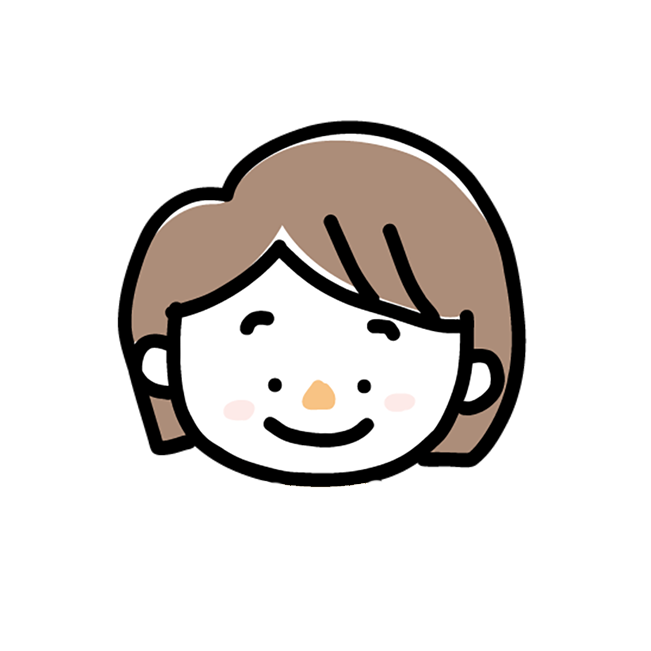 Bさん
Bさんどうしてだろう・・・
 先生
先生何か大切にしていることがあるの?
(成功の責任追及)
 Bさん
Bさん・・・
せっかくなら、楽しく過ごしたいじゃないですか
暗い顔していたって、良いことないし
うちのおばあちゃんが、そういう人だから、似たのかも
 先生
先生とても良い考え方だね
おばあちゃんも素敵な方なんだね
 Bさん
Bさんそうなんですよ!
私、おばあちゃんが大好きで
- Bさんは、自分の行動の背景や価値観を振り返り、言葉にできています
- 先生は、その価値観と大切な存在を認めることで、信頼関係を深めています
「うまくいった理由」は
質問されなければ、なかなか考えない

具体例3 問題が起こらなかったこと
~相談の場面にて~
 先生
先生Cさん、最近は表情が穏やかに見えるわ
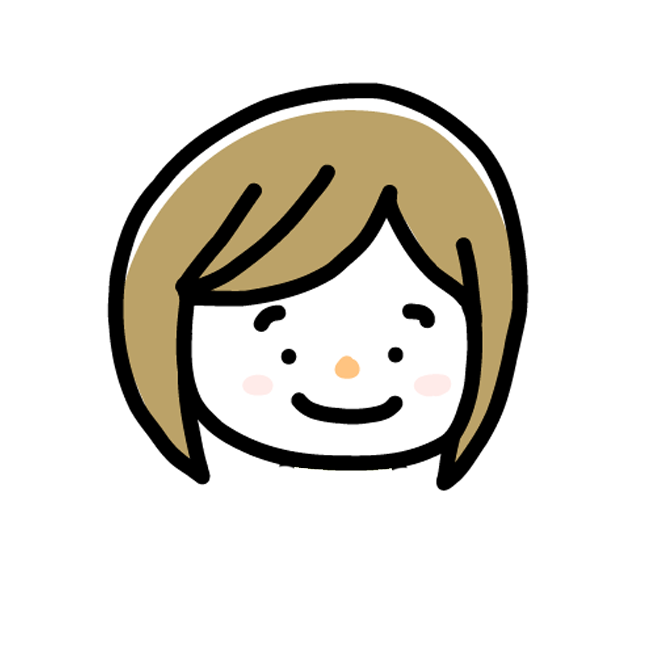 Cさん
Cさんはい。少し気持ちが安定してます
 先生
先生よかった~
どうやって気持ちを安定させているの?
(成功の責任追及)
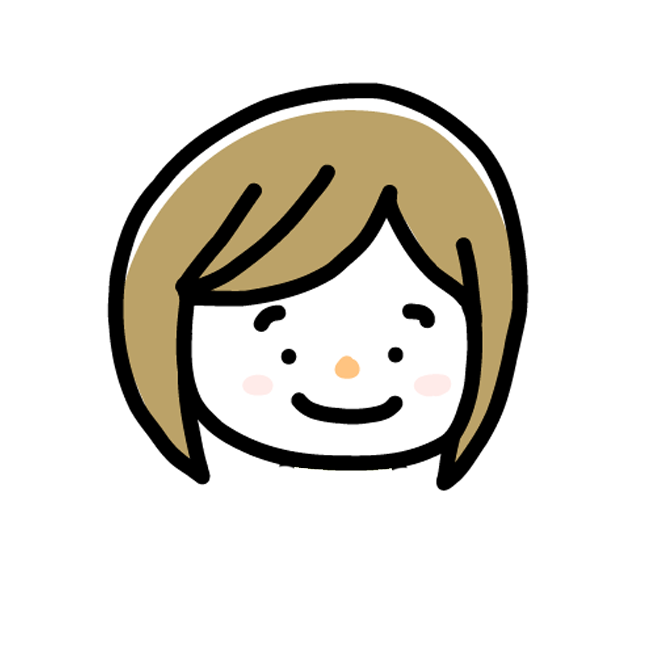 Cさん
Cさん・・・そうですね
あまり考えすぎないようにしているというか・・・
「考えても仕方ないことだな」って思うようになって
 先生
先生考えても仕方ないこと・・・
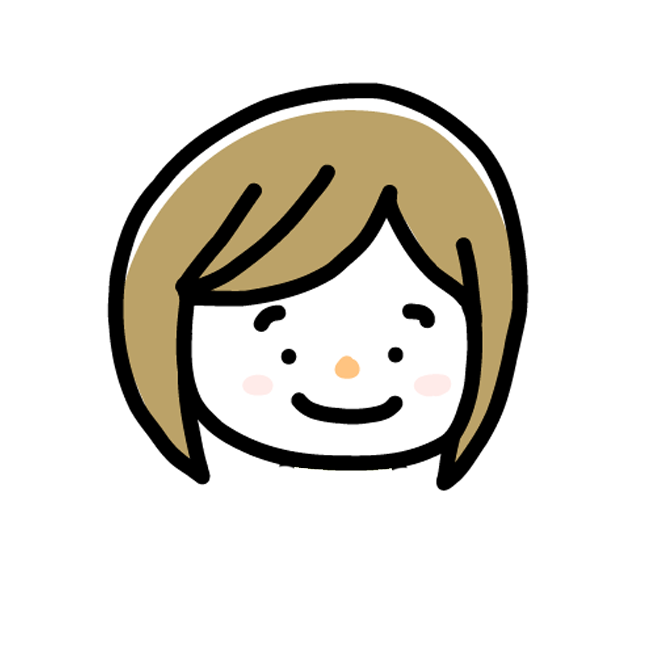 Cさん
Cさんはい。考えても疲れるだけだから
「まぁ、いいか」って思うようにしていて
 先生
先生「まぁ、いいか」って、いい言葉だね~
どうやってそう思えるようになったの?
(成功の責任追及)
 Cさん
Cさん吹っ切れたというか・・・頭に浮かんだんです
- Cさんは、自分の内面を言葉にしながら、「気持ちを整える工夫」を整理できています
- 先生は助言をせず、話を聴くことでCさんの自己効力感(自分で対処できる感覚)を高めています
役に立つのは、助言よりも
「うまくいった理由」を聴くこと

3 期待できる効果
(1)成功を「本人のお手柄」にする
「成功の責任追及」は、主語を「あなた」にする問いかけです。
- 「(あなたは)どうやったんですか?」
- 「(あなたは)どんな工夫をしたんですか?」
- 「(あなたは)どんなふうに努力しているんですか?」
この問いには、「成功を引き起こしたのはあなたです」というメッセージが込められています。
そのため、一見「たまたまうまくいった」ものであっても、
問いかけを通じて、成功を「本人のお手柄」として扱うことができます。
先ほどのAさんの例では、
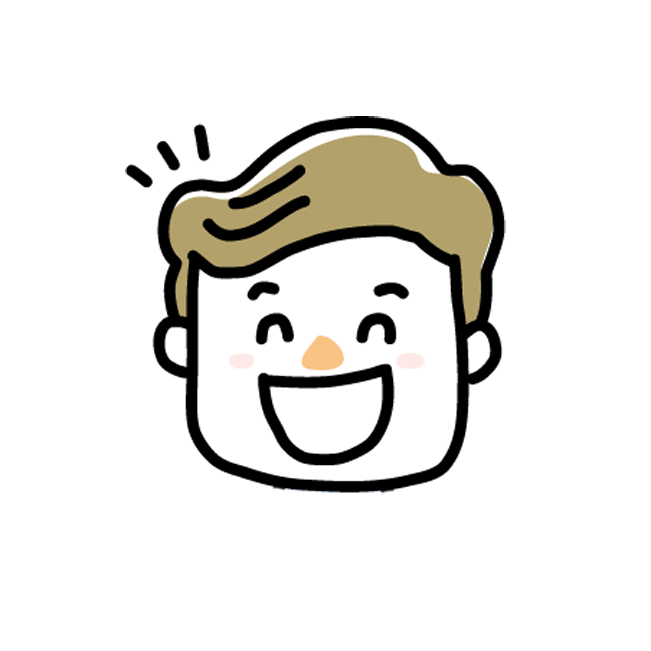 先生
先生すごいよ!がんばったね!
それで、どうやって成績を上げたの?
(成功の責任追及)
 Aさん
Aさん・・・
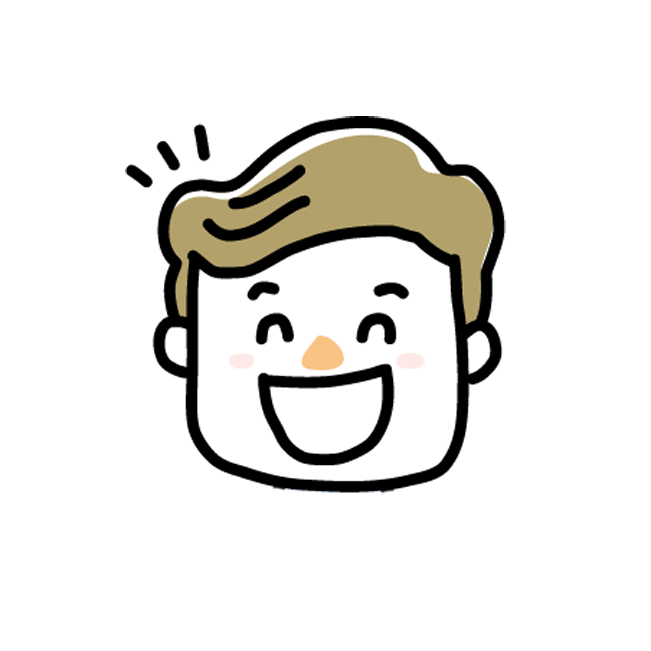 先生
先生何か変えたことがあるんじゃない?
(成功の責任追及)
 Aさん
Aさん変えたこと?
あ、少し勉強時間が増えたかも・・・
ゲームをあまりしなくなったから
Aさんは当初、「たまたま成績が上がっただけ」と思っていたかもしれません。
しかし、問いかけを受けることで、「自分の行動によるもの」という感覚が芽生えています。

(2)問いかけ自体が「賞賛」になる
NHKの番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」をご存知でしょうか?
番組の最後、エンディングテーマが流れる中で、出演者に問いかけられる有名な質問があります。
「あなたにとってプロフェッショナルとは?」
これは、日本で最も有名な「成功の責任追及」といえるでしょう。
この問いには、「あなたはプロフェッショナルです」「あなたの考え方には価値があります」
という無言の賞賛が含まれています。
同じように、
- 「どうやったんですか?」
「あなたの行動が良かった」という賞賛 - 「どんな工夫をしたんですか?」
「あなたはうまくやっている」という賞賛 - 「どんなふうに努力しているんですか?」
「あなたは簡単ではないことをやっている」という賞賛
先ほどのBさんの例も、
 先生
先生一緒にいると楽しくなるよ
どうしたらそんなふうにできるの?
(成功の責任追及)
「あなたは特別なことをしている」という無言の賞賛が含まれています。
そのため、相手は嬉しい気持ちになり、
たとえその場で答えが出なくても、あとで「うまくいった理由」を考え続けることが多くあります。

文脈と口調を誤ると、「失敗の責任追及」に聞こえる
例えば、
「半分も間違っている!どうやって勉強したの?」
「半分も正解できている!どうやって勉強したの?」
同じ言葉でも、前後の雰囲気が違えば文脈が変わり、意味は真逆になります。
問いかけの前には、しっかりと相手をほめること。
そして、少し明るい口調で、
「成功について聞きたい」という意図を相手に伝えるように心がけてください。
(3)本人が成功を「再現」できる
最後は、最も重要な効果です。
成功した理由を聴くことは、その成功を再現することにつながります。
先ほどのCさんの例では、
 先生
先生どうやって気持ちを安定させているの?
(成功の責任追及)
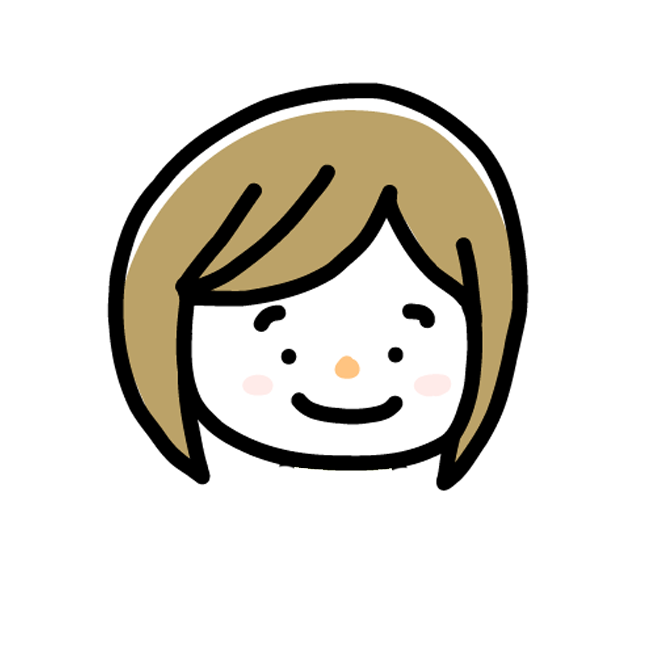 Cさん
Cさん・・・そうですね
あまり考えすぎないようにしているというか・・・
「考えても仕方ないことだな」って思うようになって
 先生
先生考えても仕方ないこと・・・
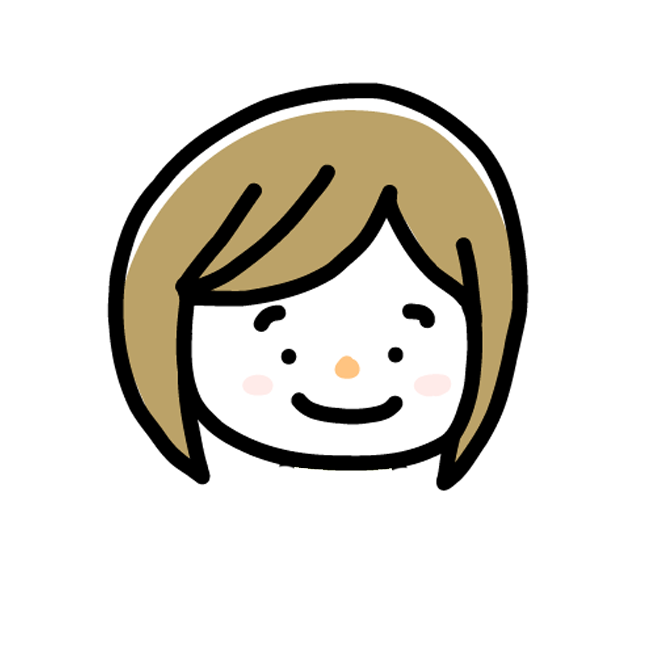 Cさん
Cさんはい。考えても疲れるだけだから
「まぁ、いいか」って思うようにしていて
 先生
先生「まぁ、いいか」って、いい言葉だね~
成功の責任追及によって、Cさんは「うまくいった方法」を言葉にできました。
ここで重要なのは、
この「うまくいった方法」は、次の成功を生むための「うまくいく方法」でもあるということです。
しかもそれは、Cさん自身が見つけたものであり、すでに成功した経験がある方法です。
成功した方法は、次に成功する方法でもある
先生が肯定的に話を聴いたこともあり、
Cさんは、おそらくこの方法を繰り返し、次はより意識的に実践していくでしょう。
成功の責任追及は、過去や現在について問いかける質問ですが、
その答えは、成功を繰り返し、未来に変化を起こすための大きなヒントになります。
成功の責任追及は、未来の成功の追求となる
成功の責任追及は
未来の成功の追求となる
未来志向の責任追及… やりたくなりましたか?

まとめ
- 「ほめ言葉+成功の責任追及」のセットで、うまくいった理由について問いかける
- 「どうやったの?」「どんな工夫を?」と問いかけると、
問いかけられた児童生徒は、自分のできていること、もっているものを探し始める - 「成功した理由」は、「次に成功するためのヒント」でもある
成功の責任追及は、児童生徒の強みを引き出し、成長を支える問いかけである
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。
PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。
次回もどうぞお楽しみに。