教育現場では、日々さまざまな問題が起こります。
それらの問題に直面したとき、指導するか?支援するか?あるいは、その両方が必要なのか?
問題の捉え方によって、児童生徒へのかかわり方は大きく変わります。
また、表面的な「行動」だけに注目してしまうと、その背後にある大切なメッセージを見落す危険もあります。
このコラムでは、問題行動の背景にある「こころの状態」に目を向けるための視点について解説します。
トラウマに関する内容が含まれています。ご不安のある方は、無理をせず、ご自身のペースでゆっくりお読みください。
内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。
このコラムは約3分で読めます。
1 心身に余裕がないとき
次のような状況をイメージしてみてください。
最近、仕事が忙しく、
まったく余裕がない。
心も体も、強い疲れを感じている。

「イメージしなくても、まさに今その状態です」という声が聞こえてきそうですね・・・(涙)。
そんなお疲れのところ、申し訳ありませんが、次の質問に答えてみてください。
- 心と体に余裕がないとき、こんなことはありませんか?
- いつも以上に、他の先生や児童生徒にイライラする
- 家に帰ると、何もやる気が起きない
- 普段はしないような間違いやミスをする
- 物事をネガティブに考えたり、なかなか決められなかったりする
- 家族に甘えたり、つい言葉遣いが荒くなったりする
・・・
これらは、多くの人が経験する「ごく自然な反応」です。
人は、心身に余裕がなくなると
イライラしたり、やる気をなくしたり、少しわがままになったりする
人は、心身に余裕がなくなると
イライラしたり
やる気をなくしたり
少しわがままになったりする

児童生徒も同じです。
特に、発達の途中にある児童生徒は、抱えた感情が行動や身体症状として表に出やすい傾向があります。
児童生徒の様子に「イライラ」「無気力」「わがまま」などが見られたときは、
もしかして、心や体に余裕がないのかもしれない
そんなふうに考えてみてください。
問題行動をすぐに指導しようとする前に、ほんの少し立ち止まり、
「もしかして、何か助けが必要なのかもしれない」
「本人は、何に困っているんだろう?」
と、心の声に耳を傾けてみてください。
投げやりな態度や指導への反発は、「SOSのサイン」である可能性があります。

2 トラウマという視点
(1)トラウマ体験とその影響
続いての視点は、「トラウマ(心の傷)」です。
「トラウマ」と聞くと、自然災害や大きな事故、性的被害などを思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし実際には、虐待、いじめ、貧困、家族の精神疾患や別離、友人の死など、
日常の中で起こり得るさまざまな出来事が、トラウマ体験(こころのケガ)につながることが分かっています。
トラウマ体験とは、
「自分ではどうにもできない」という圧倒された体験
言葉にすると、「まさか!」「どうしよう?」「何もできない…」といった感覚に近いと思います。
逃げることもできないため、「選択肢を与えられなかった体験」と表現されることもあります。
このような体験は、人が本来もっている安全感や安心感を奪い、他者への信頼感を低下させ、強い無力感を残すことがあります。
トラウマ体験があるからといって、
すべての人がPTSD(心的外傷後ストレス症)を発症するわけではありません。
しかし、医学的な診断がつかない場合でも、
その影響が認知・心理・身体・行動のパターンとして残ることは、決して少なくありません。
学校では、次のような形で現れることがあります。
- ちょっとしたことで怒ったり、叩いたりするなど、興奮状態になりやすい
- 怒っている声や車の音などを極端に怖がり、避けたり固まったりする
- 「バカにされた」「自分はダメだ」など、被害的に物事を捉えやすい
- 教師や他の生徒との距離感が近く、性的なトラブルを起こしやすい
- 自分の気持ちや考えを言葉にできず、原因のはっきりしない体調不良が続く
- 教師からほめられると、なぜか不機嫌になり、反抗的な態度を示したりする

(2)トラウマの視点でみると
例1:
過去に暴言や暴力の被害を受けてきた児童生徒が、
学校で暴言や暴力などの衝動的な加害行為を見せることがあります。
これは、トラウマの影響で警戒心が過度に高まり、
「攻撃される前に攻撃しないと危険だ」と反応した、自己防衛である可能性があります。
例2:
これまで家庭で否定され続けてきた児童生徒が、
先生からほめられた瞬間に、反発的な言葉を返すことがあります。
これは、トラウマの影響で「誰も信用できない」「自分には価値がない」という
否定的な信念を持ったことによる、もう傷つかないための拒否反応である可能性があります。
つまり、
乱暴な子は、乱暴されてきた子
拒否する子は、拒否されてきた子
トラウマの視点をもたずに、「わがまま、反抗」とみなし、叱責中心の指導を続けてしまうと、
結果的に、再トラウマ化(嫌な体験の繰り返し)を招き、問題となっている行動をさらに強めてしまう危険性があります。
まずは一旦立ち止まり、本人が「安全だ」と感じられる対応・環境を重視することが効果的です。
児童生徒の様子に「攻撃性」「衝動性」「麻痺(固まる)」などが見られたときは、
もしかして、トラウマがあるのかもしれない
と考えてみてください。
トラウマが影響していたとしても、暴言や暴力が許されるわけではありません。
行動を容認するのではなく、その行動の背景にある考えや気持ちを理解しようとする姿勢が大切です。
トラウマの視点をもって児童生徒を理解することは、
先生自身のストレスを軽減し、燃え尽き(バーンアウト)を予防することにもつながります。
トラウマについて学びたい方は
↓ ↓ ↓
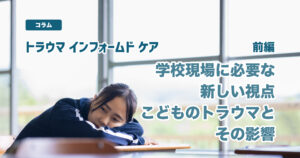

3 症状のもつ意味
最後に、「問題行動」の背景に目を向ける視点として「症状のもつ意味」を紹介します。
自閉症研究で知られる児童精神科医 レオ・カナー(L, Kanner)は、
こどもに現れる症状には、主に5つの意味があると述べています。
これは症状だけでなく、「問題行動」を理解する際にも役立つ視点です。
(1)入場券(チケット)
例えば
- 腹痛を訴えて保健室に来たが、話をしているうちに家庭の悩みを語りはじめた。
- 学習の悩みで相談に来たが、実際には友人関係の話が中心だった。
このように、表面的な症状や訴えは、こどもが先生の前に現れるためのきっかけであり、
言い換えれば、心の世界に入るための「入場券」のような役割を持つことがあります。
そのため、表面的な症状だけを取り除いても不十分であり、背景に目を向けることが重要となります。
(2)シグナル(SOSのサイン)
例えば
- 最近あまり先生に近づかないので声をかけたら、いじめの被害があった。
- 「死ね」と暴言を吐いたので丁寧に話を聴くと、家庭内で虐待を受けていた。
これらは、「今、何かが起きている」というSOSのサイン=シグナルです。
身体の「痛み」と似ています。
足が痛くて調べたら骨折が見つかるように、問題が起きていることを知らせる役割を担っています。
(3)安全弁
「安全弁」とは、より深刻な事態を防ぐための”逃し口”のような役割です。
例えば
- リストカットを繰り返すことで、「死にたいほどのつらさ」をなんとかやり過ごしている。
- 長時間ゲームに没頭することで、現実の苦しさから自分のこころを守っている。
その行動があるから、より深刻な状態をなんとか回避できているという見方ができます。
本人が自分を守るために取っている対処であるため、一方的に否定するだけでは解決につながりません。
(4)問題解決の手段
例えば
- 警察に補導されるような行動を通して、両親の不仲を解決しようとしている。
- 授業中に騒ぐことで、勉強が苦手であることを隠そうとしている。
これは、本人なりの「問題を解決するための手段」としての行動です。
適応的なものもあれば、不適応的なものもありますが、
本人にとっては「今の自分が取れる唯一の方法」であることが少なくありません。
(5)厄介者
症状は、周囲にとって「困りごと」や「迷惑」と受け取られがちです。
また、周囲が適切に対応できない場合、その役割を果たすために、症状が強まることさえあります。
表面に見える「行動」は、理解しやすいように見えますが、
そこに込められた「メッセージ」は、とても分かりにくいものです。
理解しようと向き合うことは簡単ではなく、苦しさを伴うこともあるでしょう。
それでも、「理解しよう」とする先生の姿勢そのものが、
児童生徒にとって大きな「返答のメッセージ」になるかもしれません。
ーー「あなたの気持ちを知りたい」
とても強くて優しいメッセージです。

まとめ
- 児童生徒の「困った行動」に直面したときは、「本人は何に困っているのだろう?」「何か助けが必要なのかもしれない」と想像してみる
- 「困った行動」の背景には、トラウマの影響が隠れている場合がある。「乱暴な子は、乱暴されてきた子」の可能性を考える
- 問題行動の奥にある「本人なりの理由」や「隠れた事情」に目を向け、理解しようと試みる
第2回は、発達障害(神経発達症)の「困った人は困っている人」について解説します。
続きはこちら
↓ ↓ ↓

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考になりましたら、ぜひ勤務先やSNSでシェアしていただけますと幸いです。
PSYCLA(サイクラ)は、臨床心理学・心理学の理論・技法を、教育現場で活用しやすい形に再構成し、わかりやすい情報としてお届けしています。
次回もどうぞお楽しみに。

